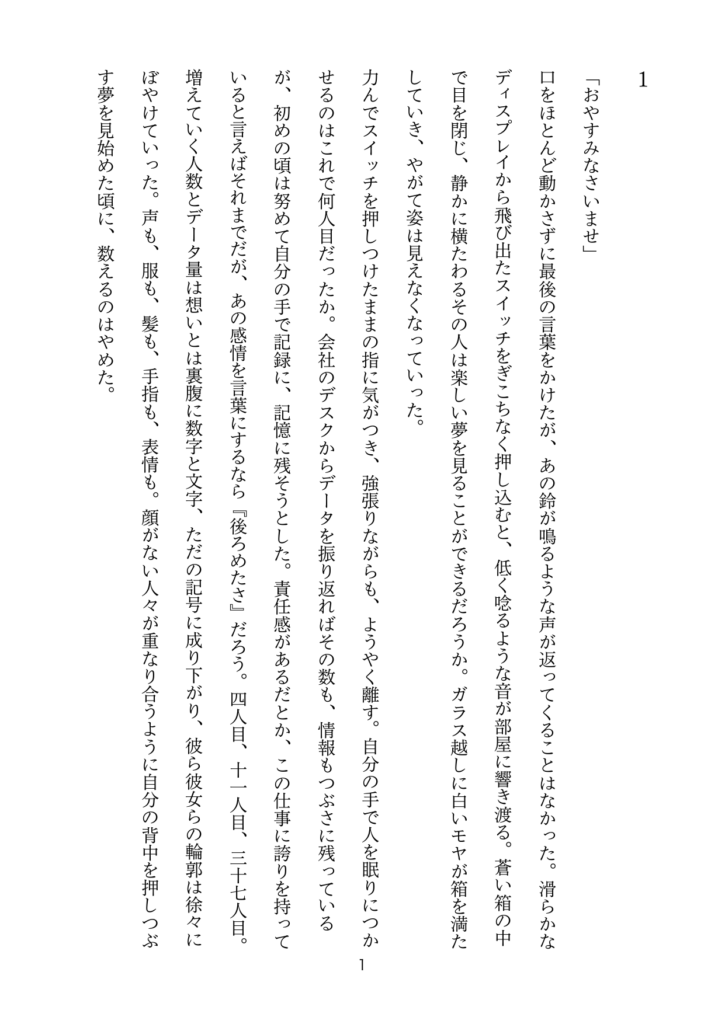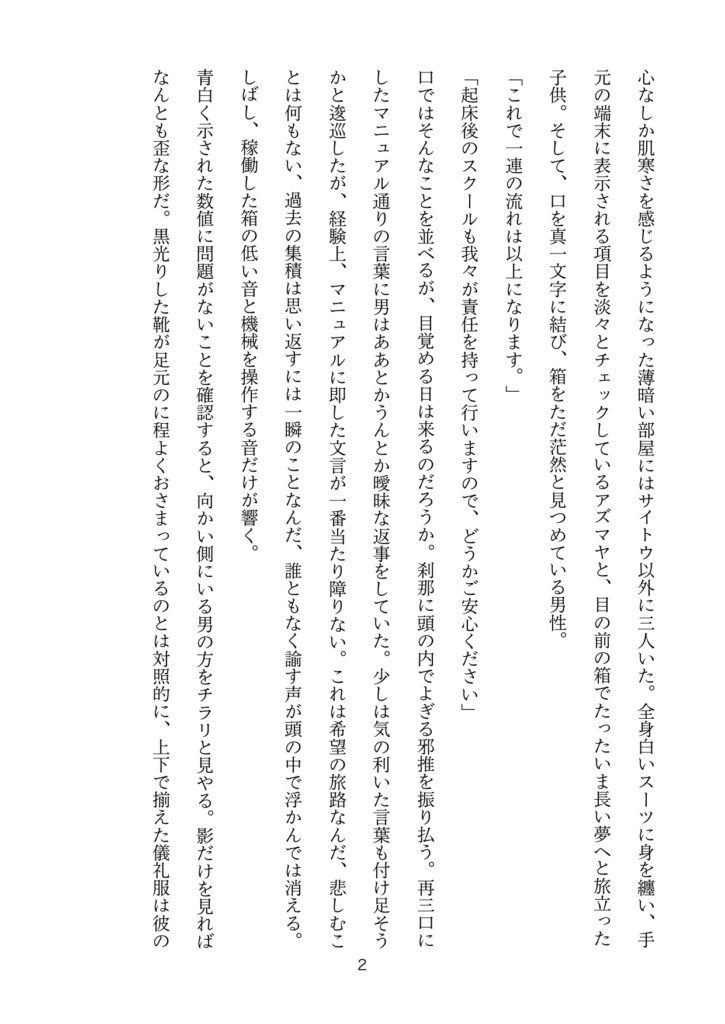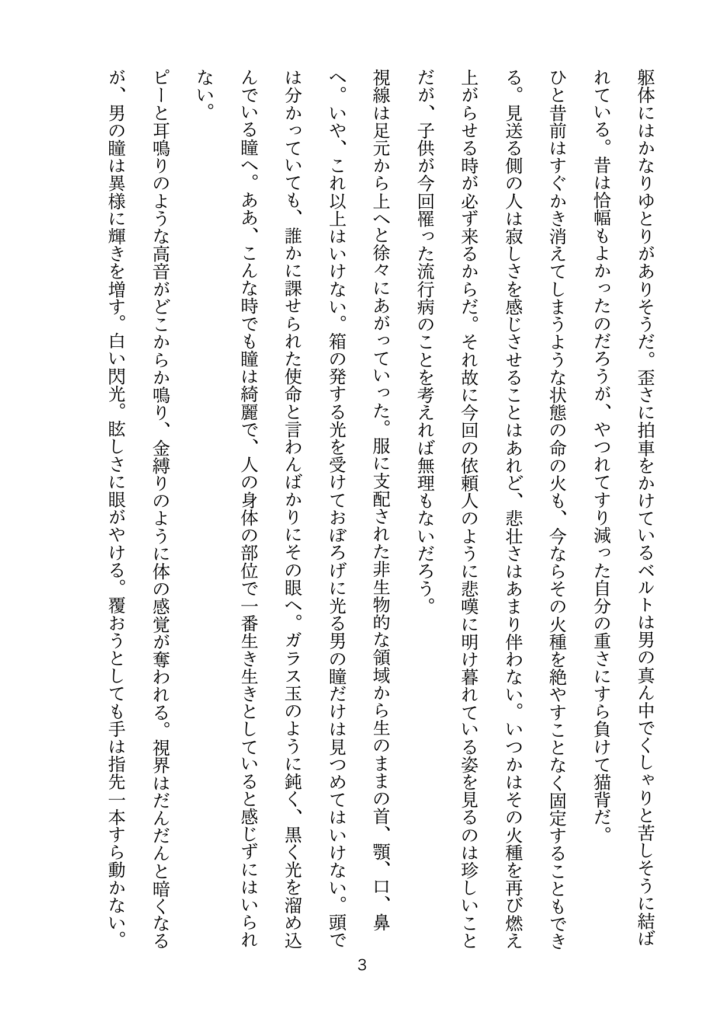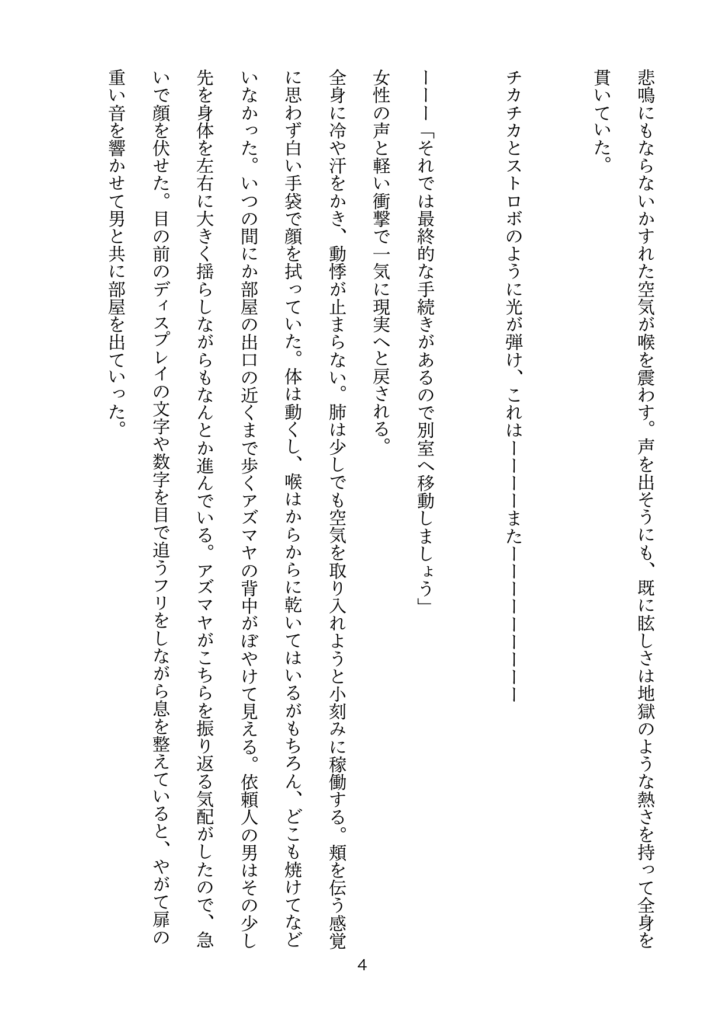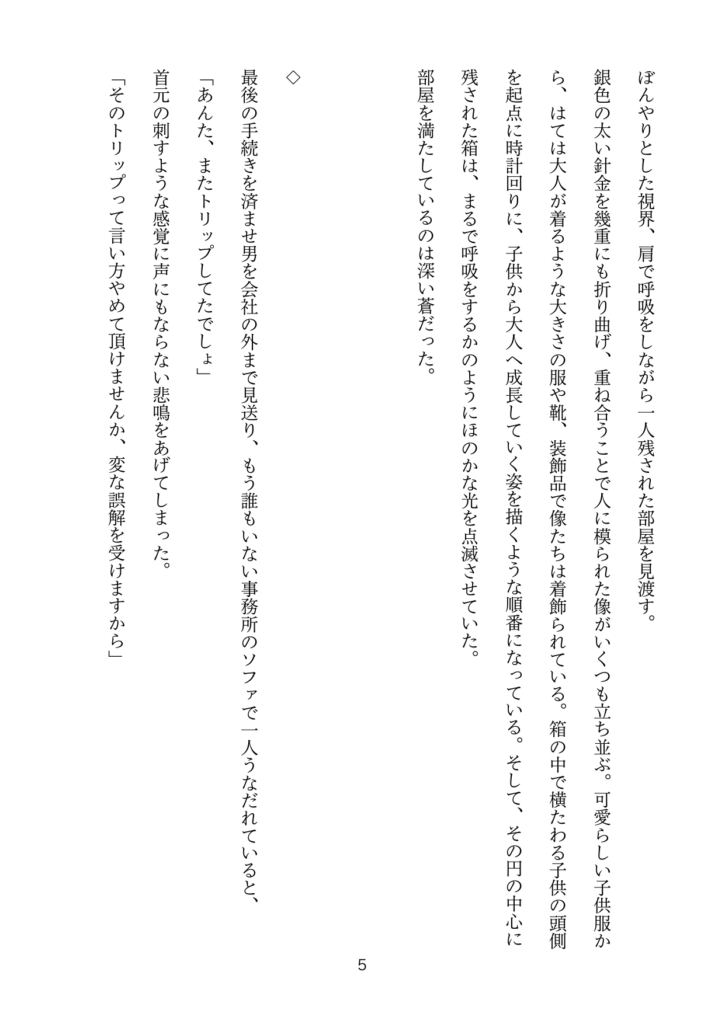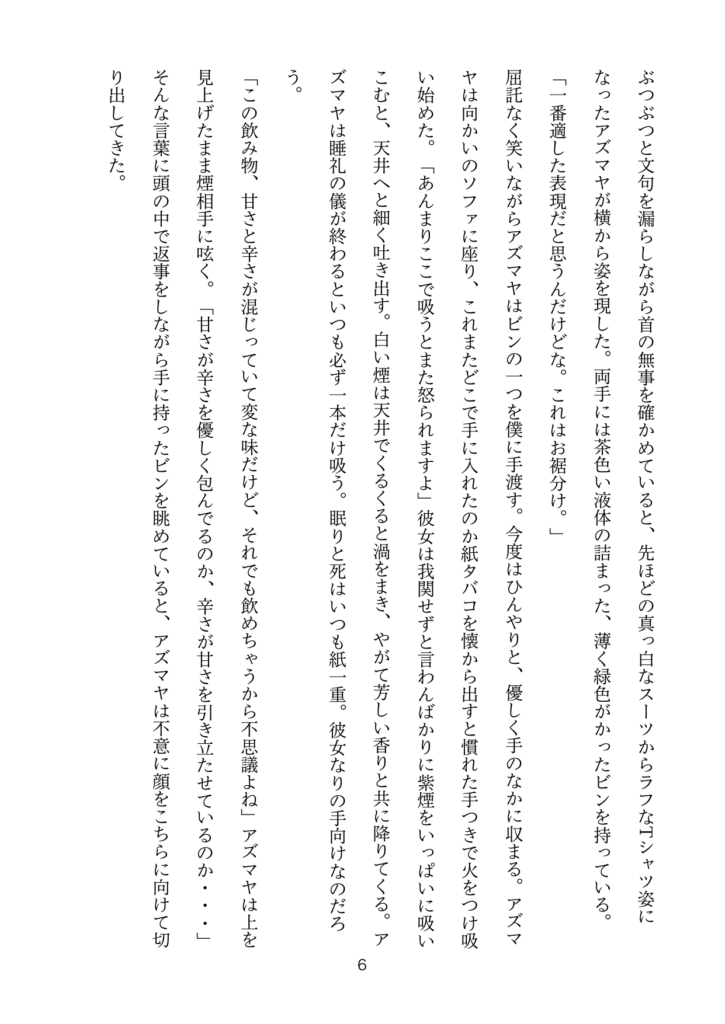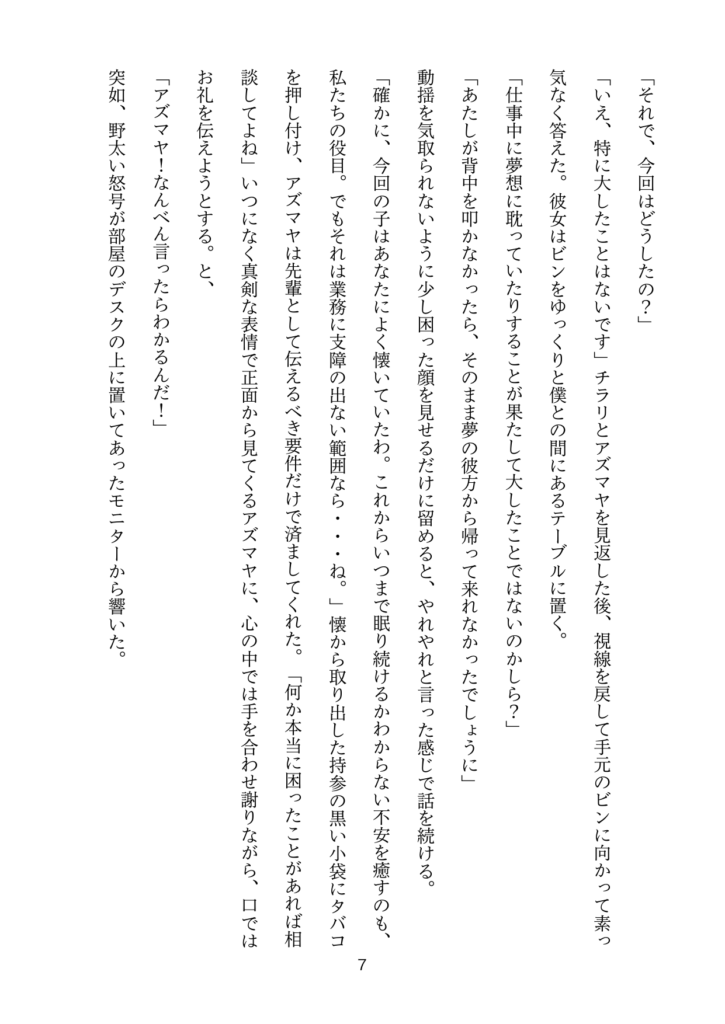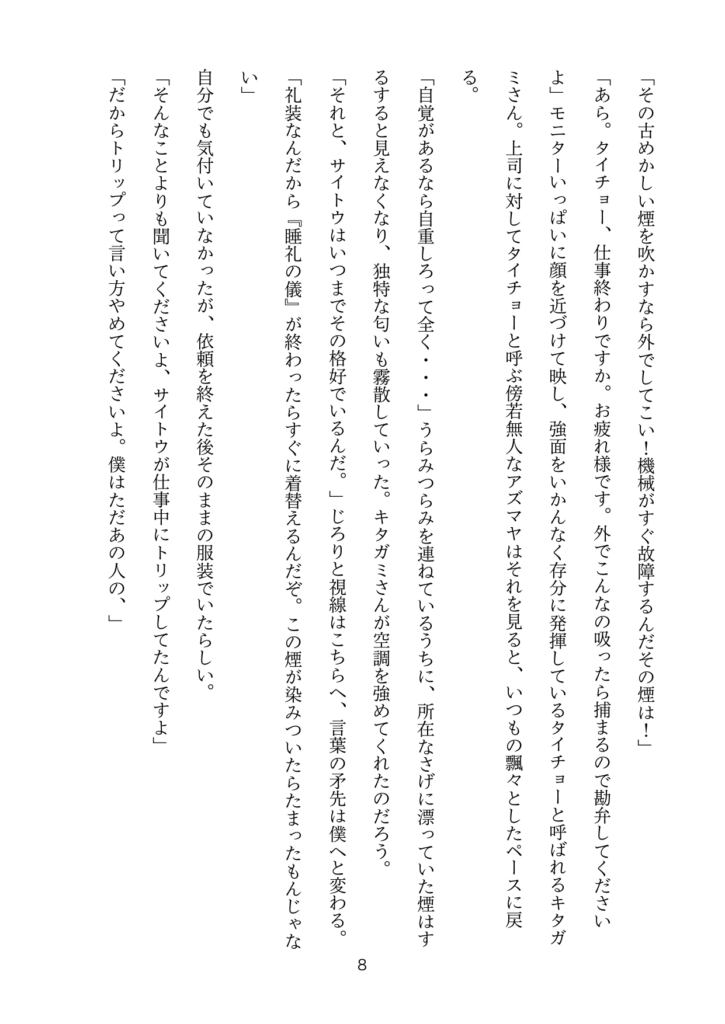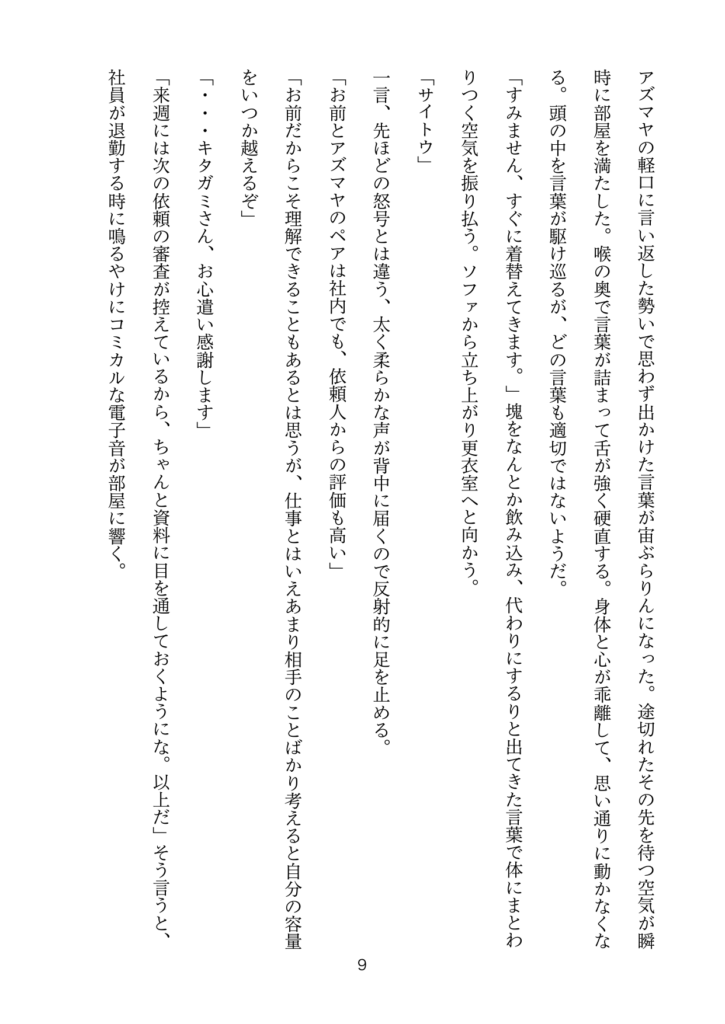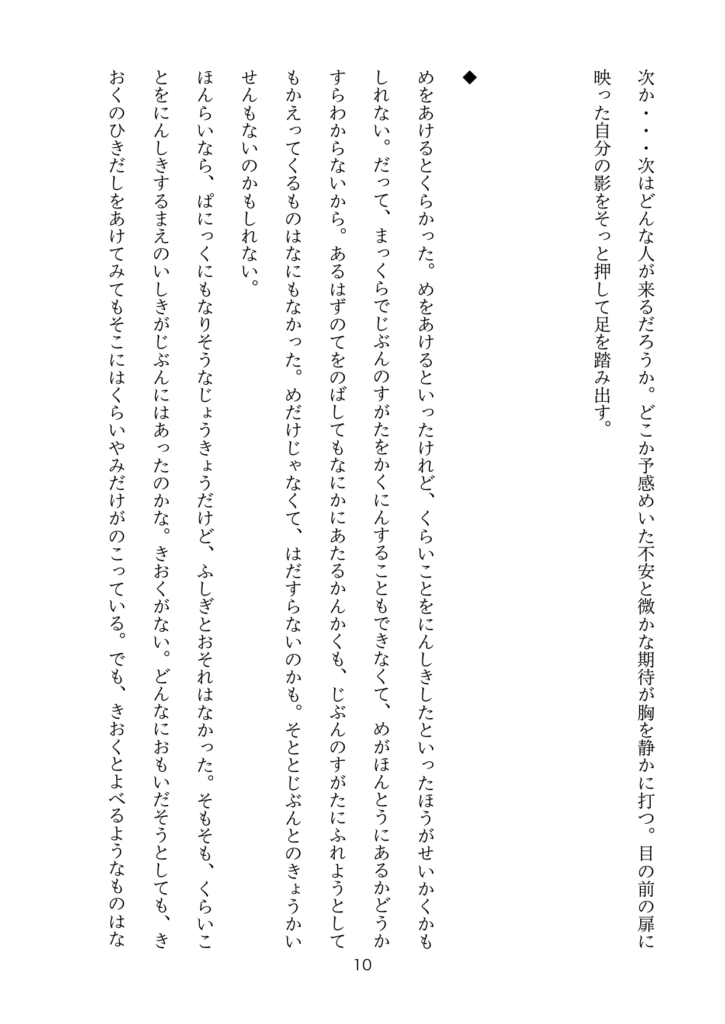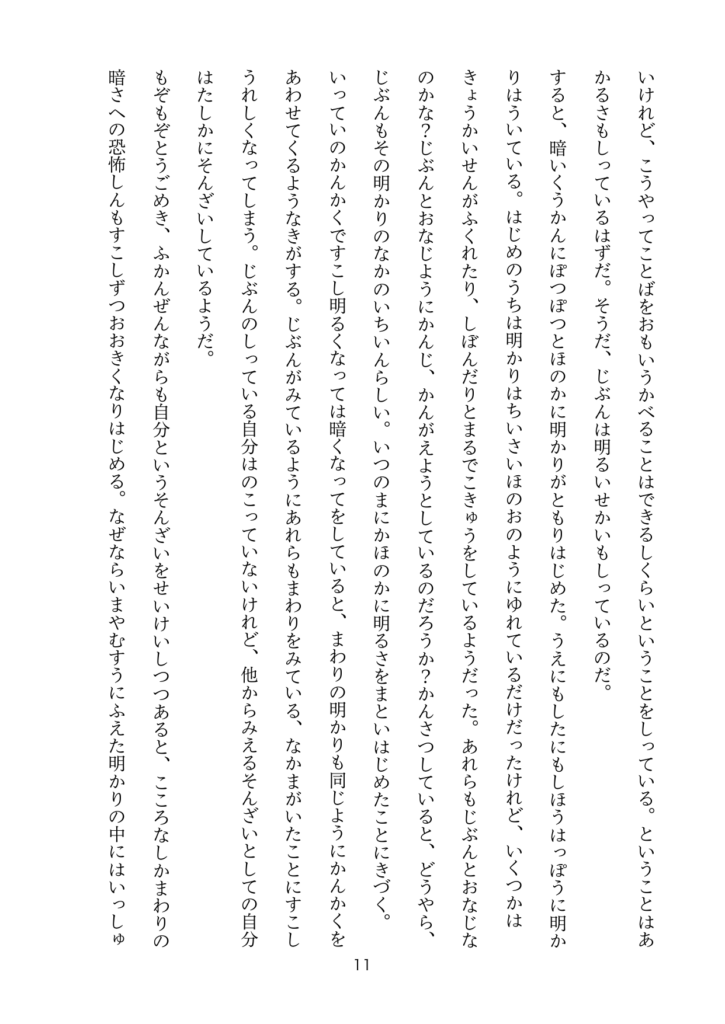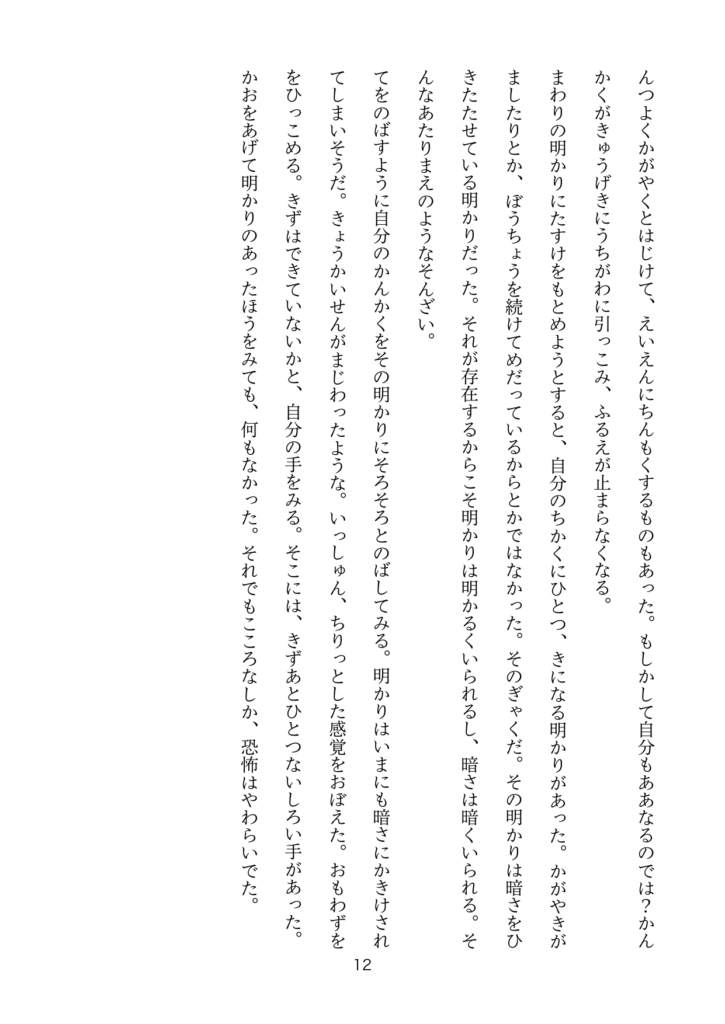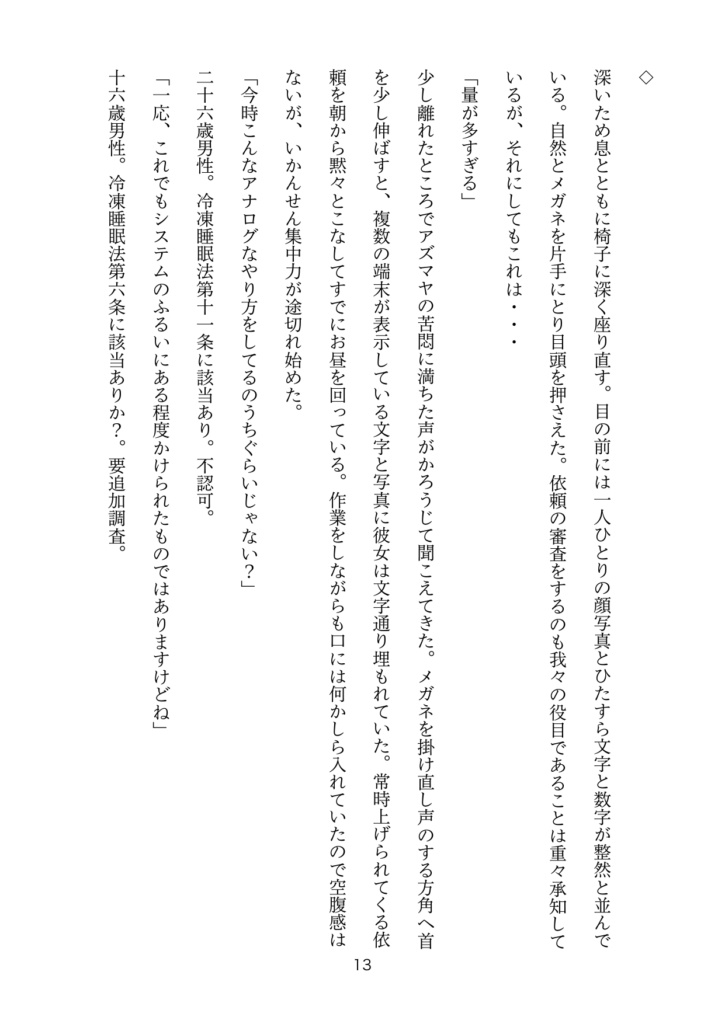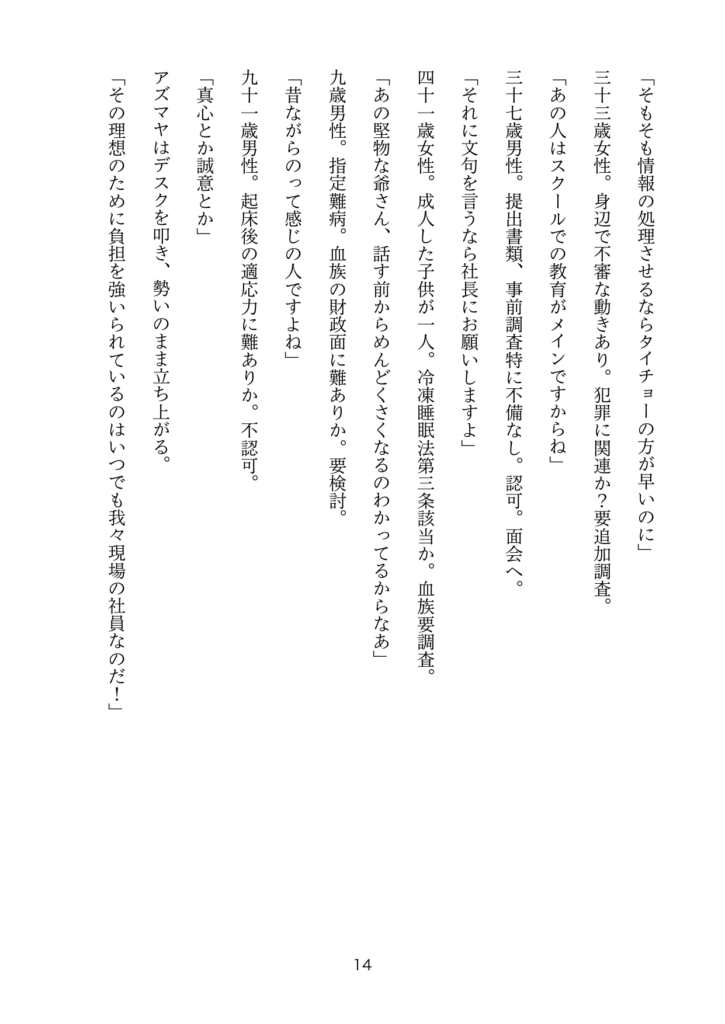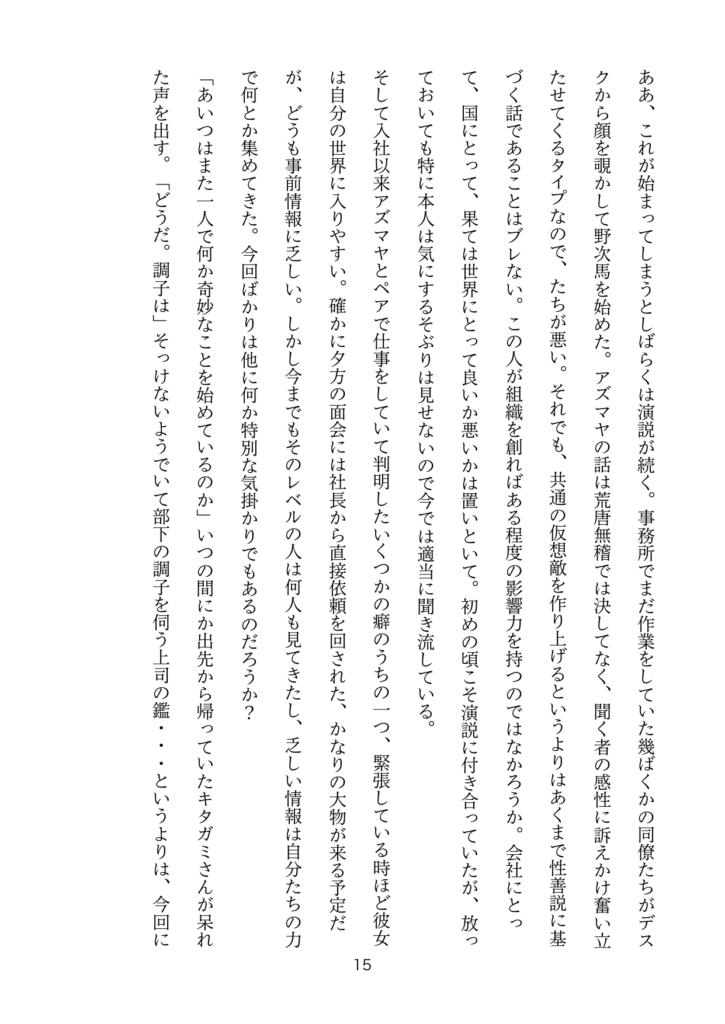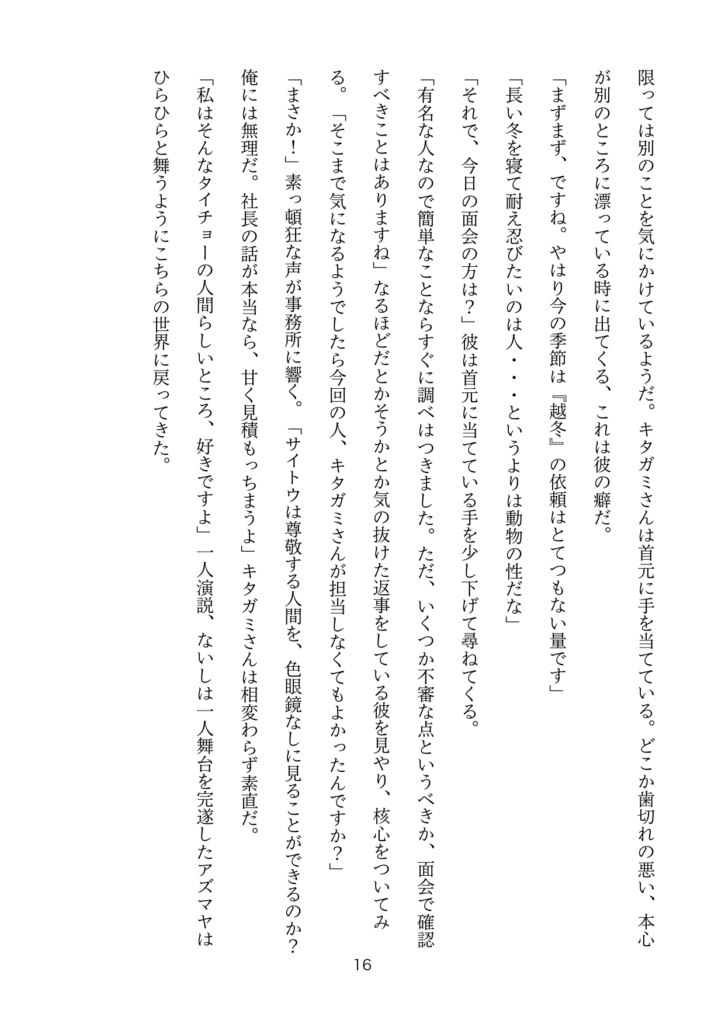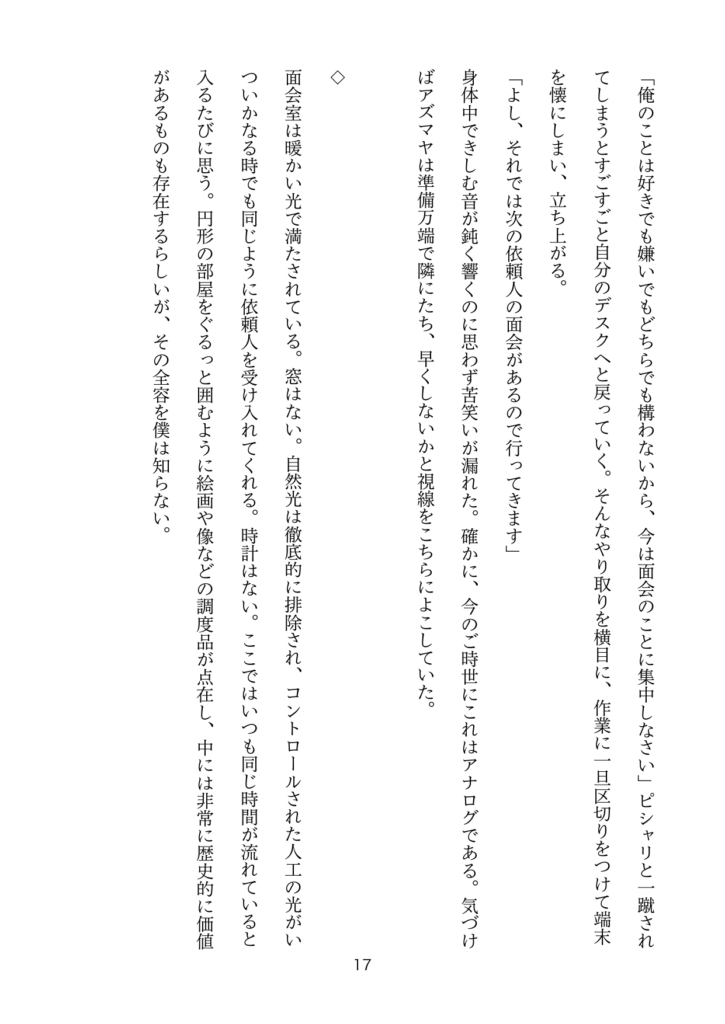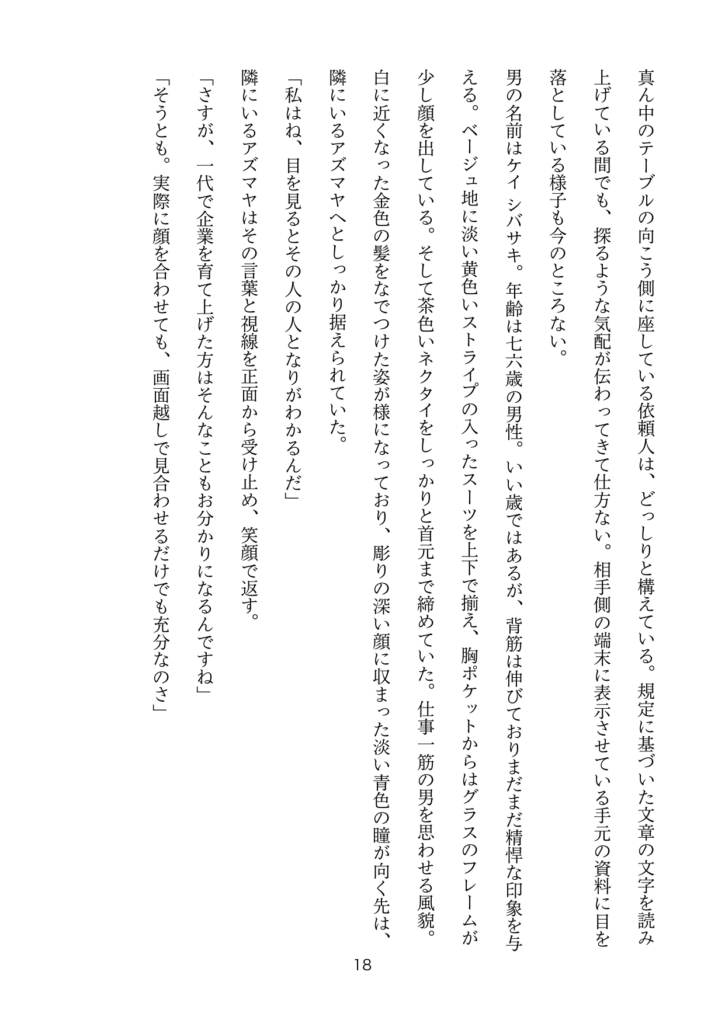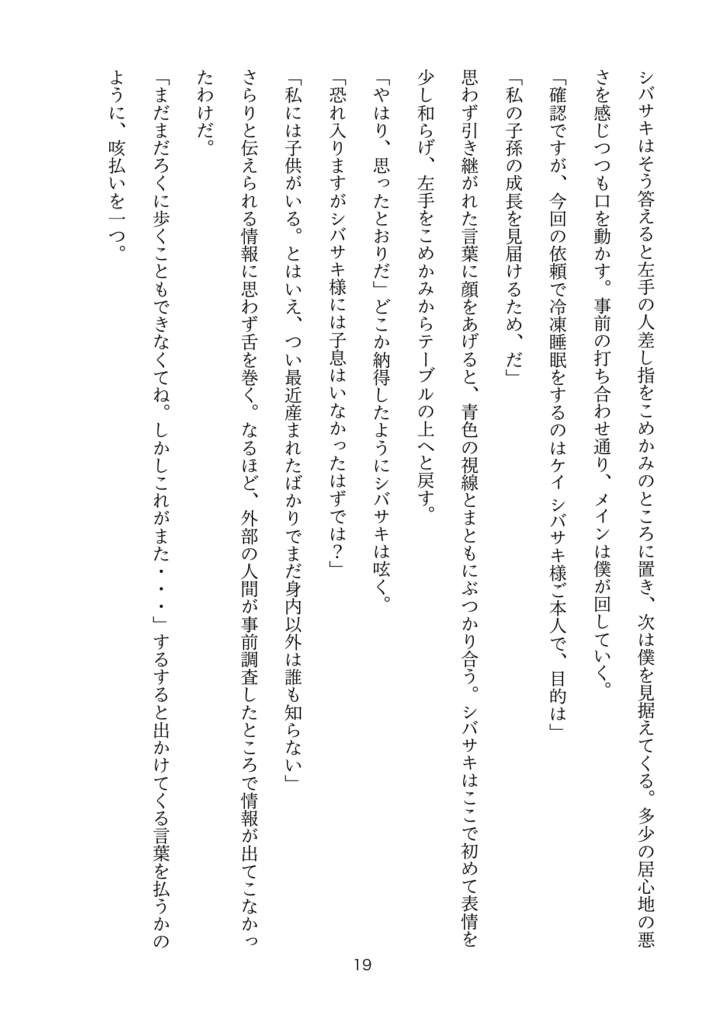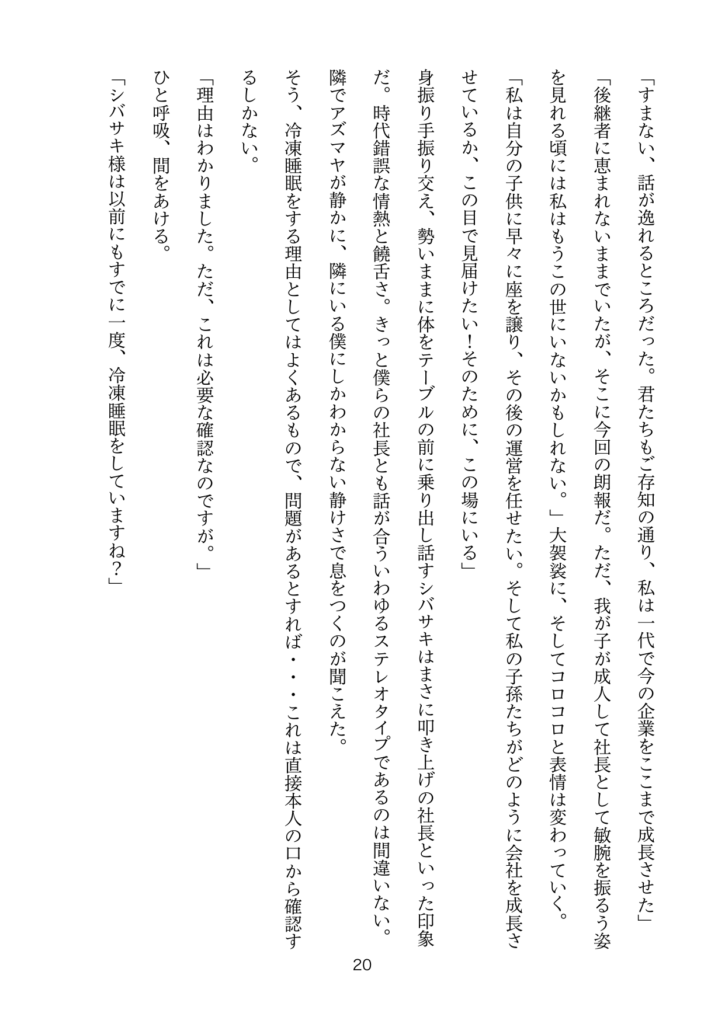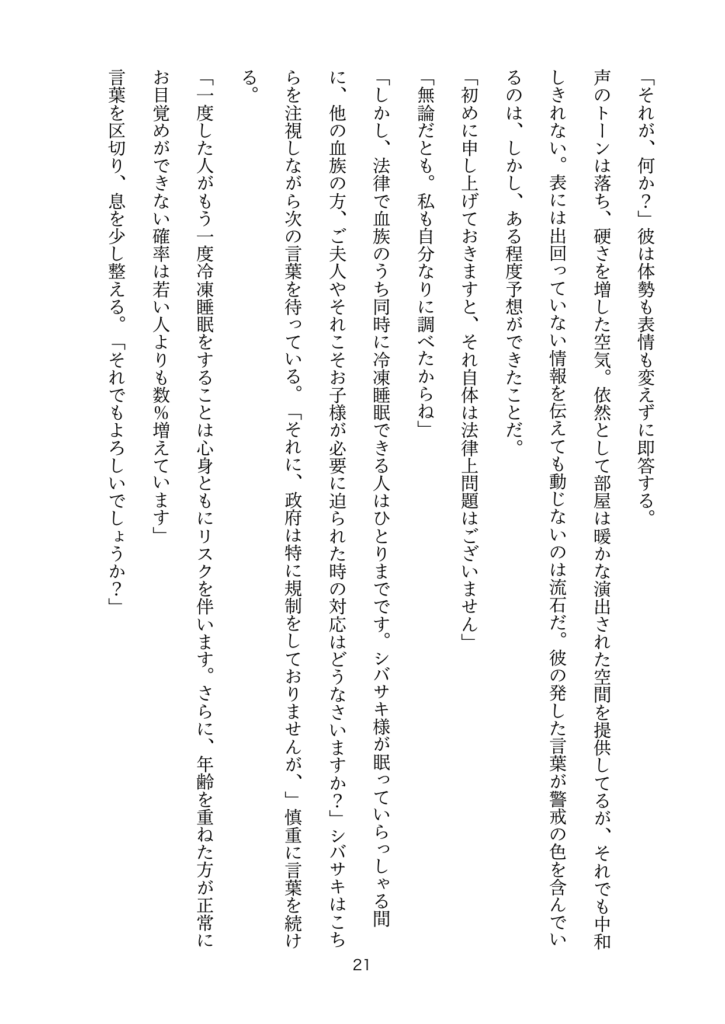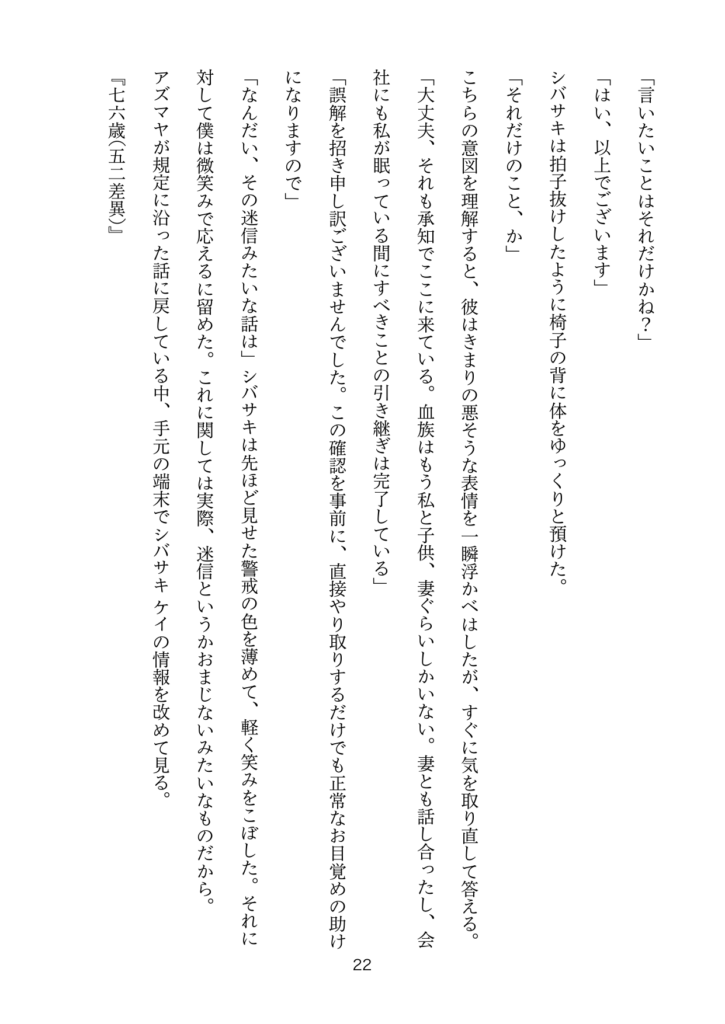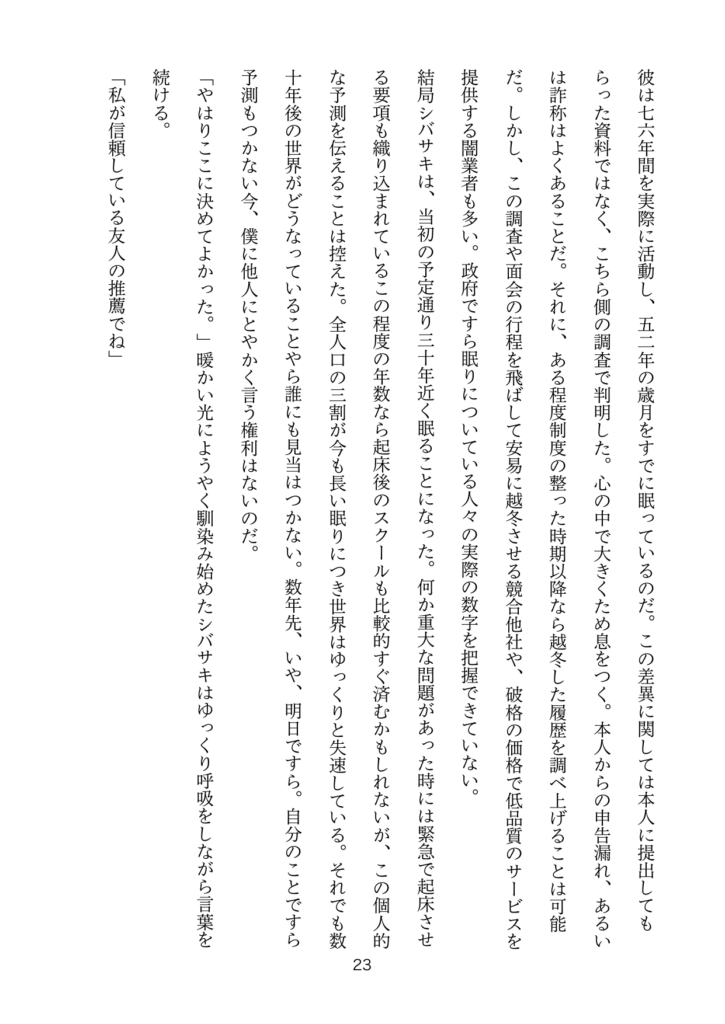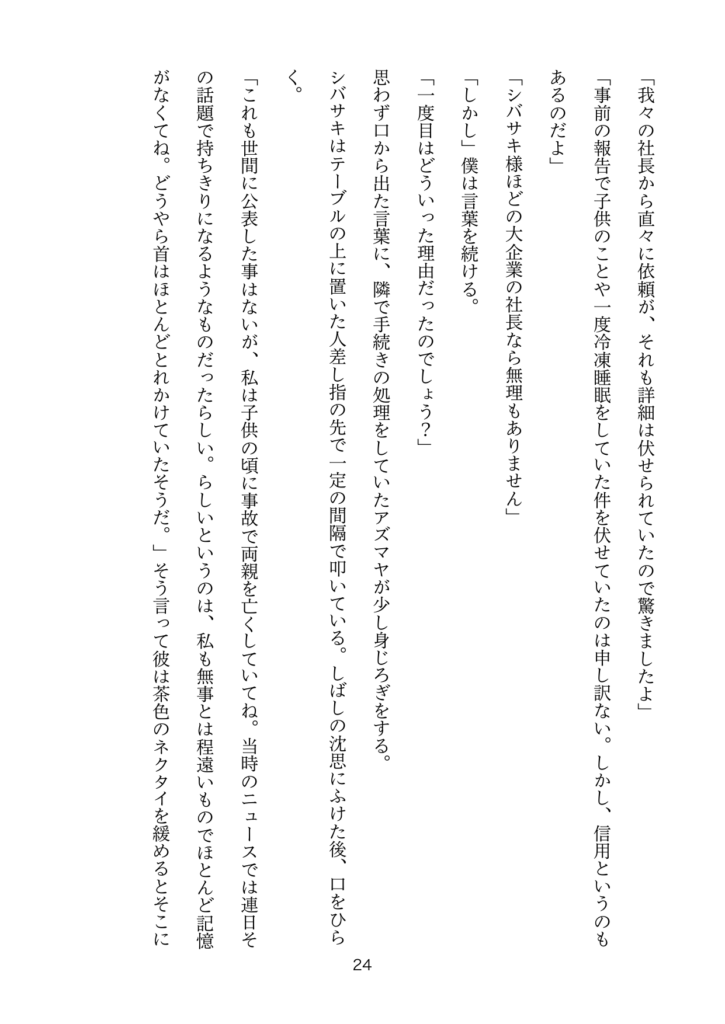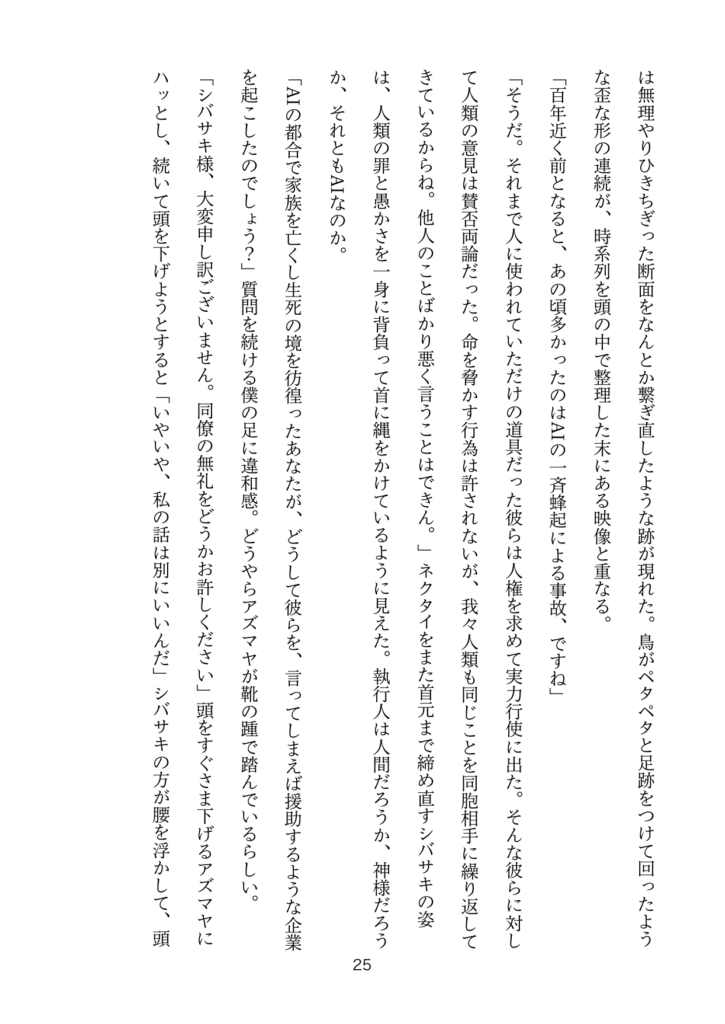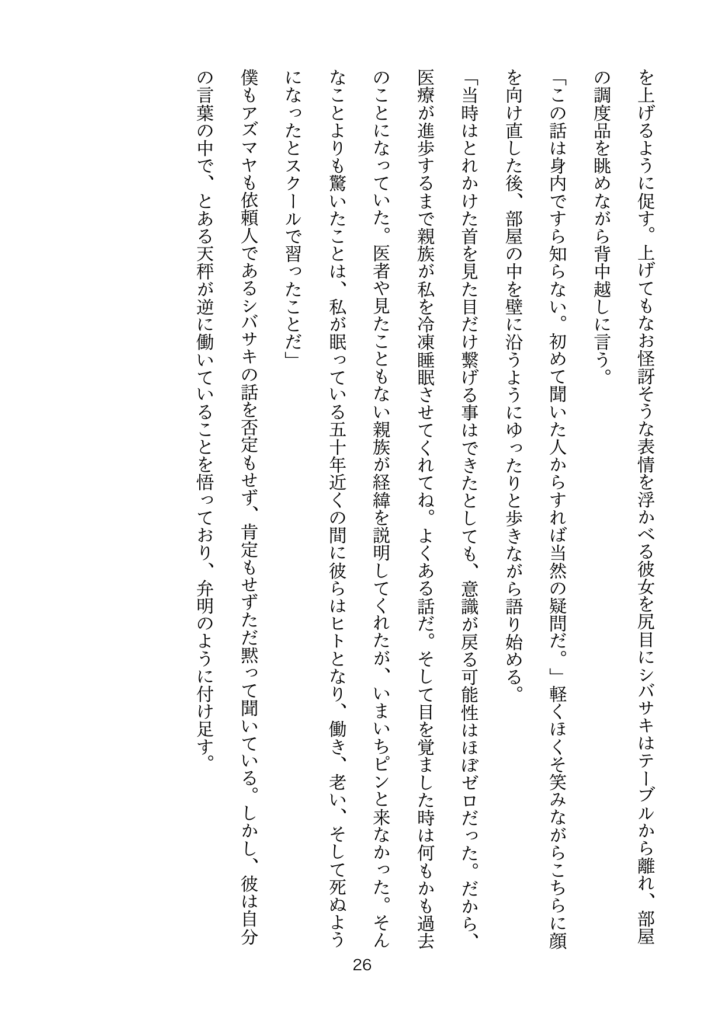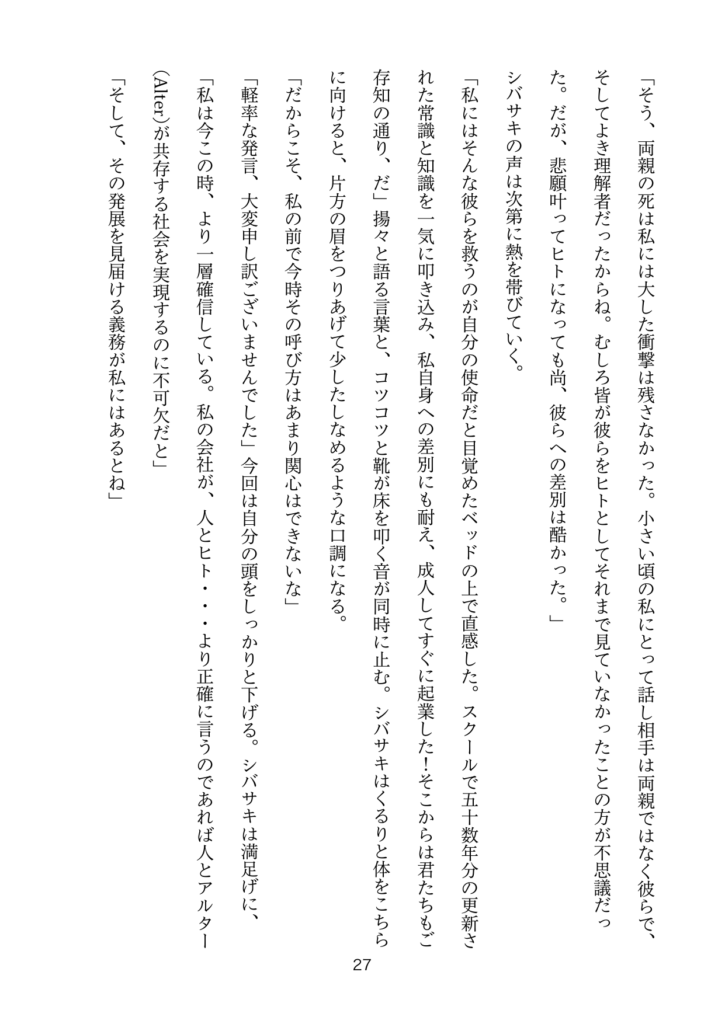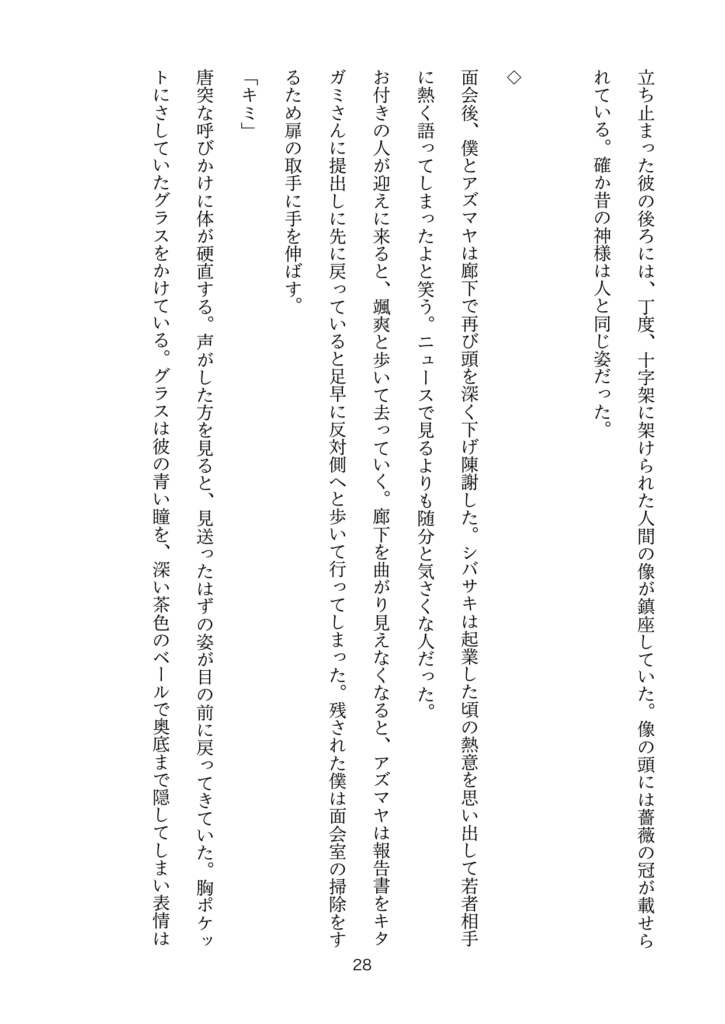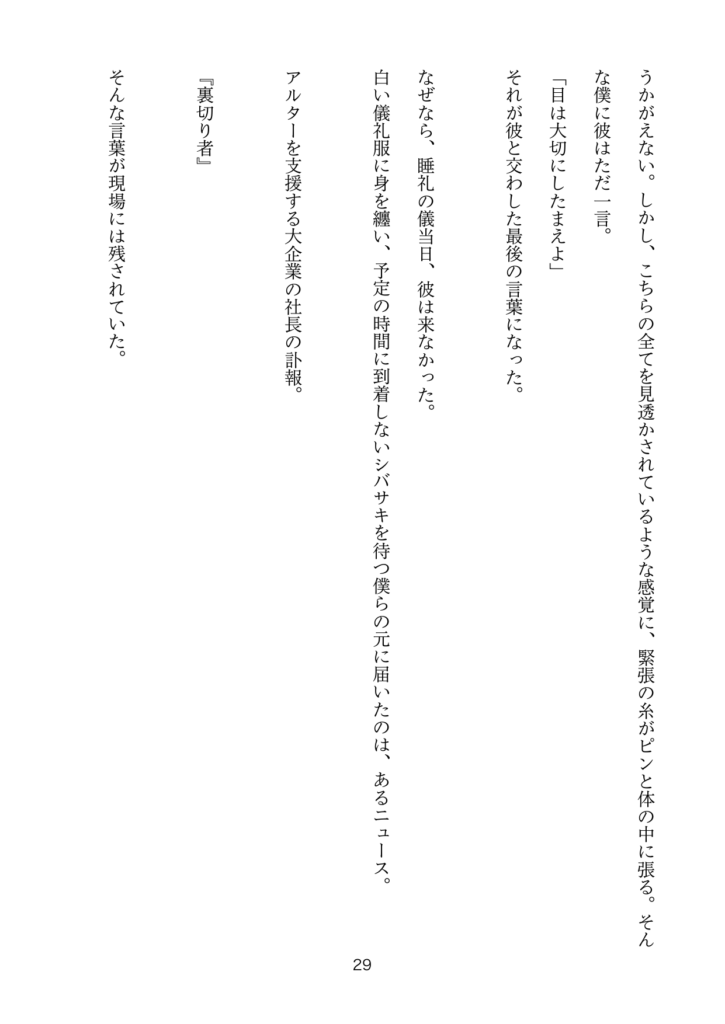殺生的な暑さ!!
-
-
空きっ腹に微糖の缶コーヒーを流し込む。ブラックにしなかったのは食べ忘れた朝食の分、なけなしのカロリーを少しでも摂取するためだ。そんな時私はいつも、野生動物たちがその日を生きていくためのカロリーを摂取するのに奔走し、人里に降りたりする光景を想像してしまう。私たち人間がその日食べれるか食べれないか気にすることはそうそうない。飲み水もそうだ。当たり前のように享受しているが、本来の自然界のことを考えると異常だ。そして、そんな当たり前を破壊する戦争が歴史の教科書の中でなく、実際に今起きている。テレビやスマホの画面の向こうの世界で、自分には他人事に思えるかもしれないが確実に暗い足跡は迫ってきている。そこまで考えていると、缶コーヒーは半分に、目的地は半分のところまでやってくる。これもまた、日常だ。
-
電車に揺られる。都会の電車はなんだか座るのが億劫になるので、吊り革につかまり立ちながら。隣にいる旧友も同じように揺られている。十年近くぶりの再会は、分別をわきまえ始めた年頃よろしく、社交辞令の真似事なんかをするばかりでどんな会話をしたものか。正直覚えていない。ただ、お互い制服から浮いた黒いネクタイを首元までしっかりしめていた。
人というのは年長者から順番通りに死んでいくものとばかり思っていたので(今思えばそれはとても恵まれている世界なのだろう)、同年代の旧友の死の知らせは全くの実感の欠落を伴ったままだった。母親づてに聞いていた彼の成長は、幼心に残っていたやんちゃな彼とは違う、すばらしい秀才さを物語っていた。書き記している今も、記憶の中の小さい彼と静かに横たわる大きい彼のイメージがどうも繋がらない。努力して繋げようとすると、とある女子生徒の悲痛な声が蜃気楼のような記憶をいつも引き裂いてしまう。周りには同じ制服を着た仲間たちが寄り添い合っていた。おそらく同級生なのだろう。私と旧友はつぎはぎの繋がりで、かろうじて隣り合う座布団の上で正座をし、心の中で推測することしかできなかった。その悲しみを共有できない自分を薄情だなんて卑下したりはしない。それでも、時の流れと、生と死の逆行にただぽつねんと取り残され、漂流する感覚が残っていた。
この記憶と感覚を記すことに抵抗はある。ここに書いては消し、忘れた頃に書いては消した。しかし、その人のいなくなった空白の存在を確かめ、感じることは必要だ。文字にすることは、固定することだ。そして固定したそれは過去でもあり未来でもある。時空を超えることができる。
葬式は残された者たちのためと、祖父の式の時に思った。そして、適度な距離を保ちつつ、優しく死を教えてくれるのが彼ら先達者たちだ。その敬意を忘れたりはしない。
-
抜け殻、器、社、休符
不在が存在の証明をしてくれる、ま
想いを馳せる時
人として充足しうる時
-
不在こそが存在への確かな証なのだ
-
「自分が事態を支配するのではなく、事態が自分を支配するのである」
と、かの偉大な大統領は言うのであった。
-
ああ、終わらないでほしい。
いつまでもこの時間が、続けばと。
しかしいじらしいもので。
終わりを予感してるから今が楽しいんだ。
そう感じさせられずにはいられない。
-
食べるということはつまり死をもたらすことで
それを一日三回
いただきますとごちそうさま
死を身近に感じてこその、生だと
忘れてはいけない、生
-
兄弟キョウダイ
姉妹シマイ
それなら3人は?4人は?
兄と妹、姉と弟は?
誰も教えてはくれないワケカタの話