沈んでは浮いて。
泳いでいると言うよりは溺れていないが正しい。
水の表面での息継ぎの仕方は教われど、人生の表面でのやり方は、なんだ?
当たり前のように生きることの凄さを僕らは気がついていない。
沈んでは浮いて。
泳いでいると言うよりは溺れていないが正しい。
水の表面での息継ぎの仕方は教われど、人生の表面でのやり方は、なんだ?
当たり前のように生きることの凄さを僕らは気がついていない。
煮えたぎる湯を電気ポッドで沸かし、コーヒー豆を目分量でミルに放り込み、どの豆でもメモリ4〜5の間の荒さでひいて、カップに直接置いたドリッパーにフィルターを敷き、その洗い立てのTシャツのような白の上に黒茶の粉を落とし、とんとんと少しならしてから(人差し指の第一関節まで埋めて、コピルアックと唱えてもよし)、電気ポッドから白銀のケトルにお湯をバトンパスし、ろくに冷まさずにすぐに乾いた砂丘へと注ぎ、濡れそぼって色が濃くなった大地が浮き始めたら一度注ぐのをやめて、湯気が地獄のように浮かんでいくのを見下ろして、気がついたら何回かに分けてお湯を注いでいく、ケトルが軽くなってどれどれとドリッパーを外すと、カップには並々と黒い底なし沼が現れる。怠惰なりの儀式的な朝の迎え方である。
feeling
thinking
writing
reading
Q. What’s the common thread among them?
ランニングをしていると普段は目にとまらないものが見えてくる。朝でも、昼でも、夜でも。世界が自分のあずかり知らぬところで、素知らぬかおで巡っている無数の流れの一つに身を投じる感覚。
ランニングの記録はちょうど今日で通算280回。別段、毎日とか2日に一回とか週に一回とか、ルールは設けてないので5年目にしては少ないほうだろう。旅先など各所の記録も含まれるが、近所を走ることが多いから200回は同じコースを回ってると考えてよいだろう。
広げた地図(紙の地図は現存するのか?)の上を、200回もぐるぐると描いた線の重なりだけではただの歪な環。しかし、同じ場所をぐるぐるしてるだけなのに全く同じランニングはなかったと断言できる。
熟れ落ちそうに首をもたげる椿の花、見えずとも確かにそこにいる金木犀の花、腕を広げ全てを包み込む桜の花、そして無。
人も同じだ。
春が来る頃に(仮題)2 1→コチラ
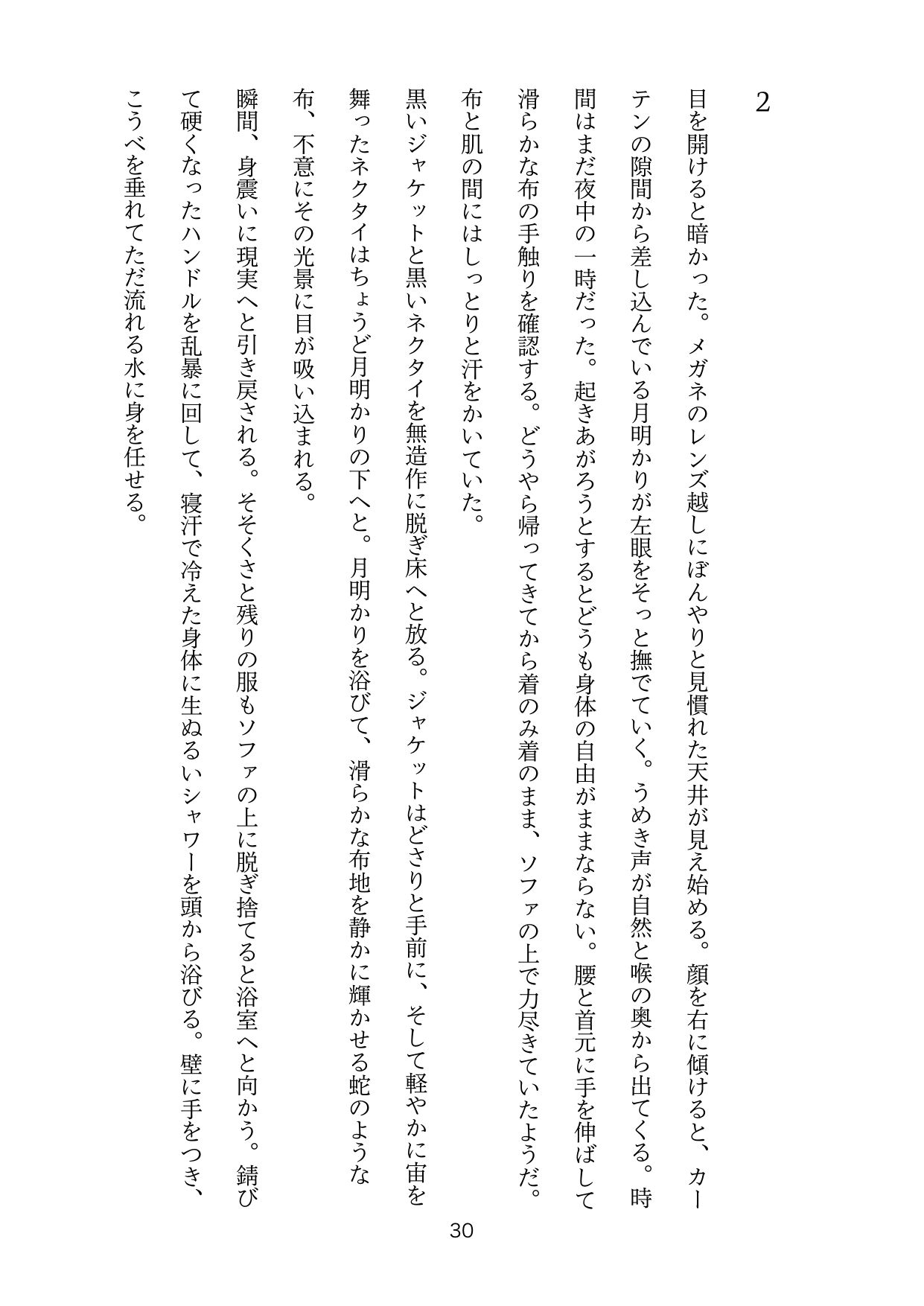
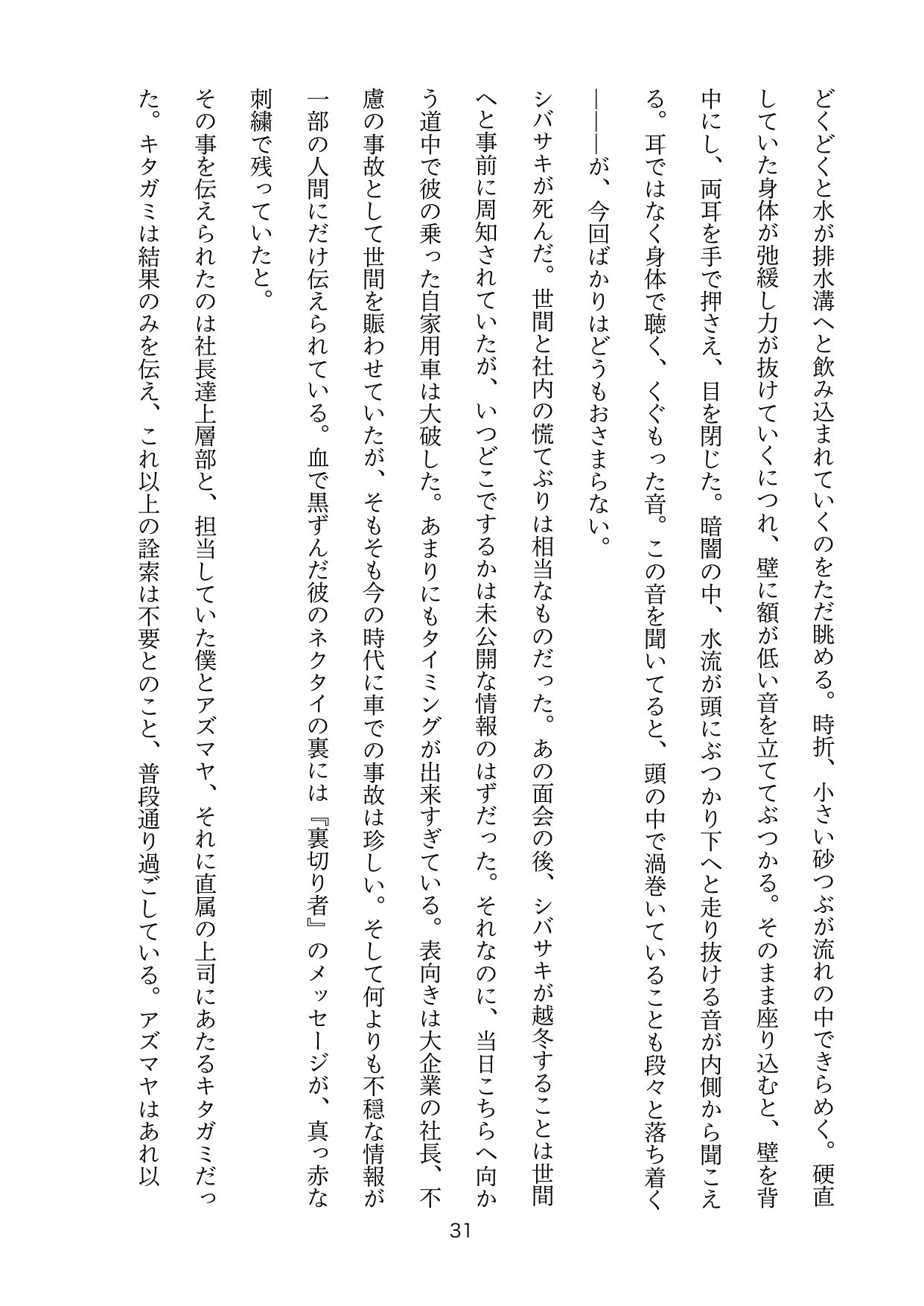
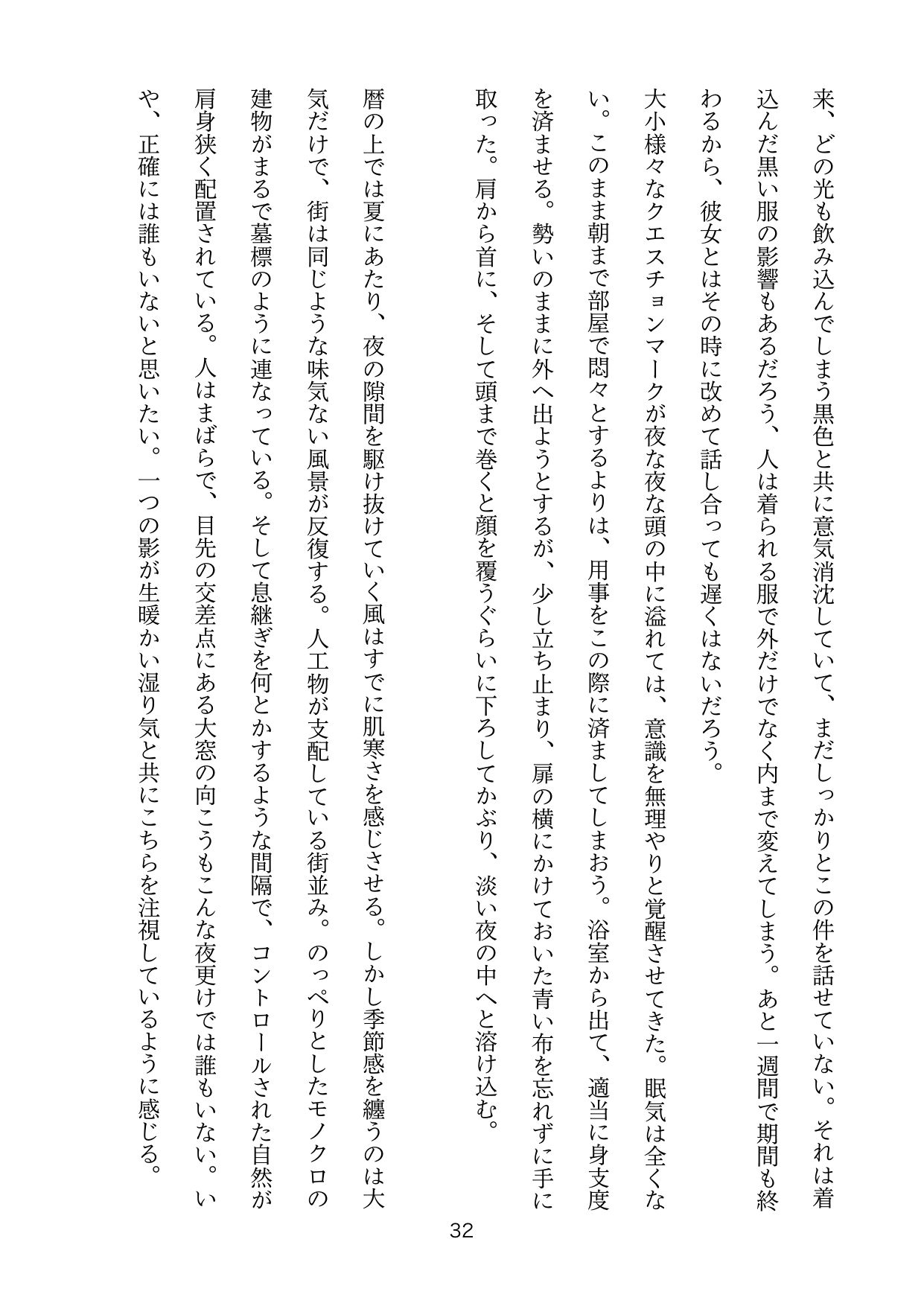
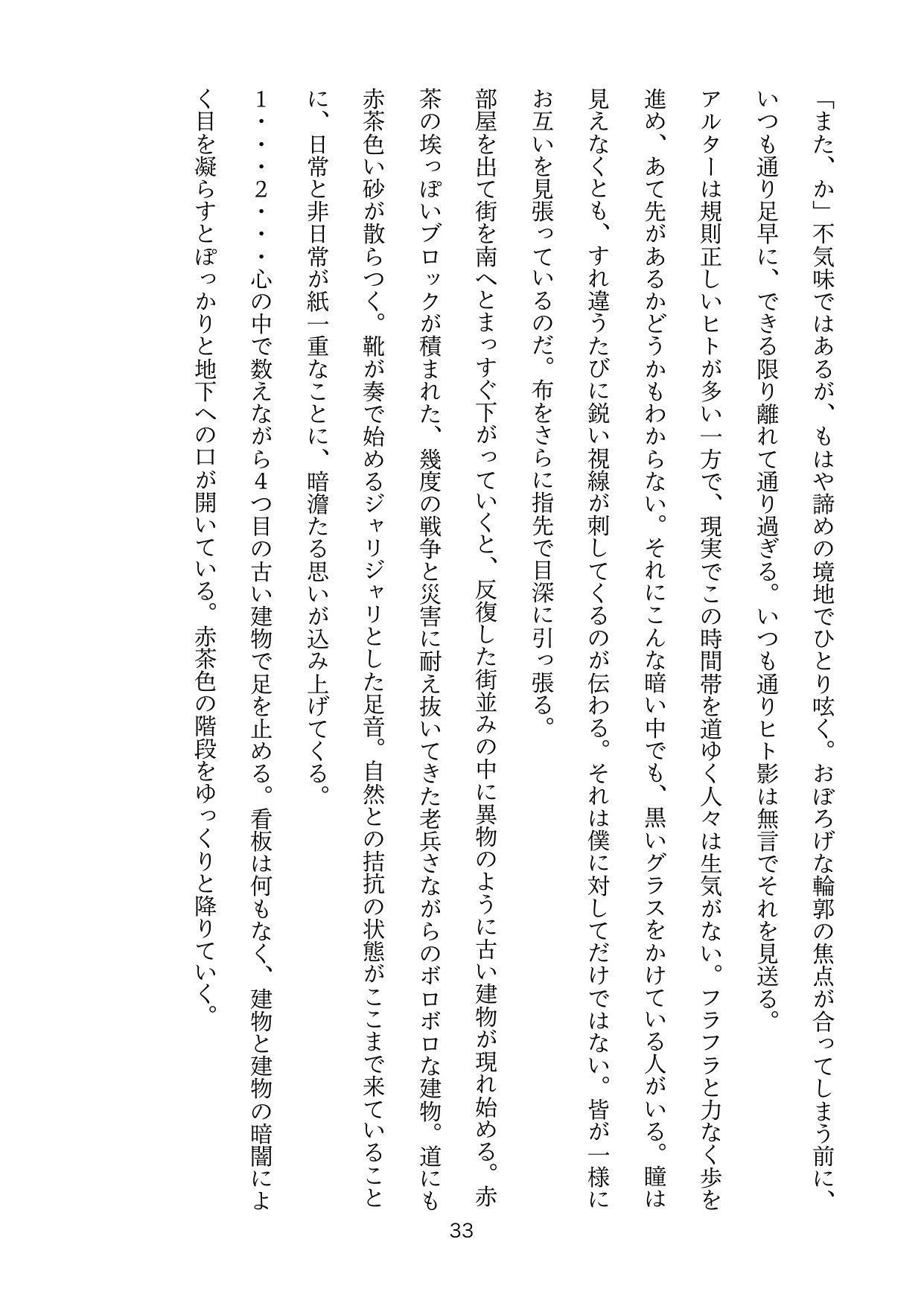
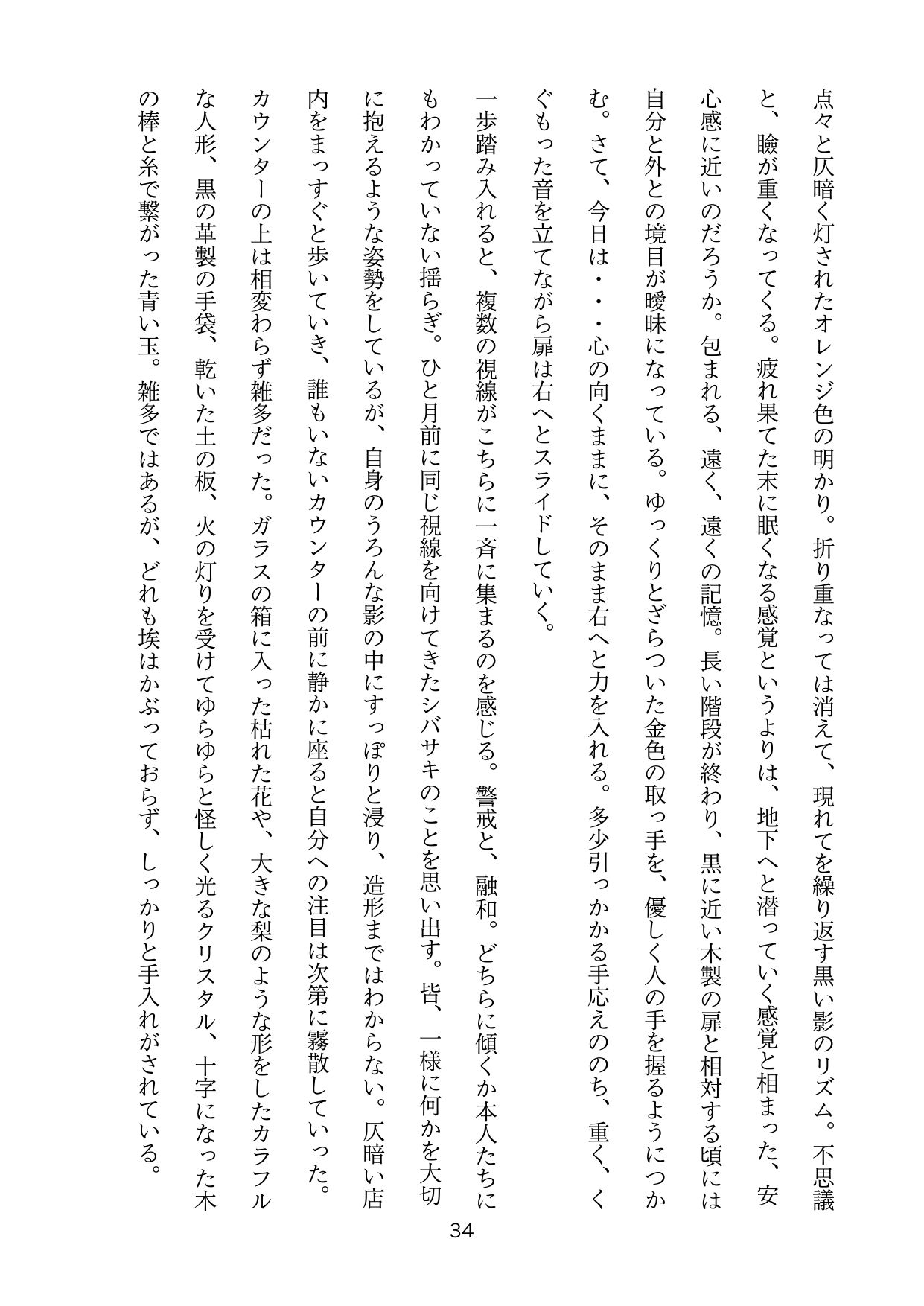
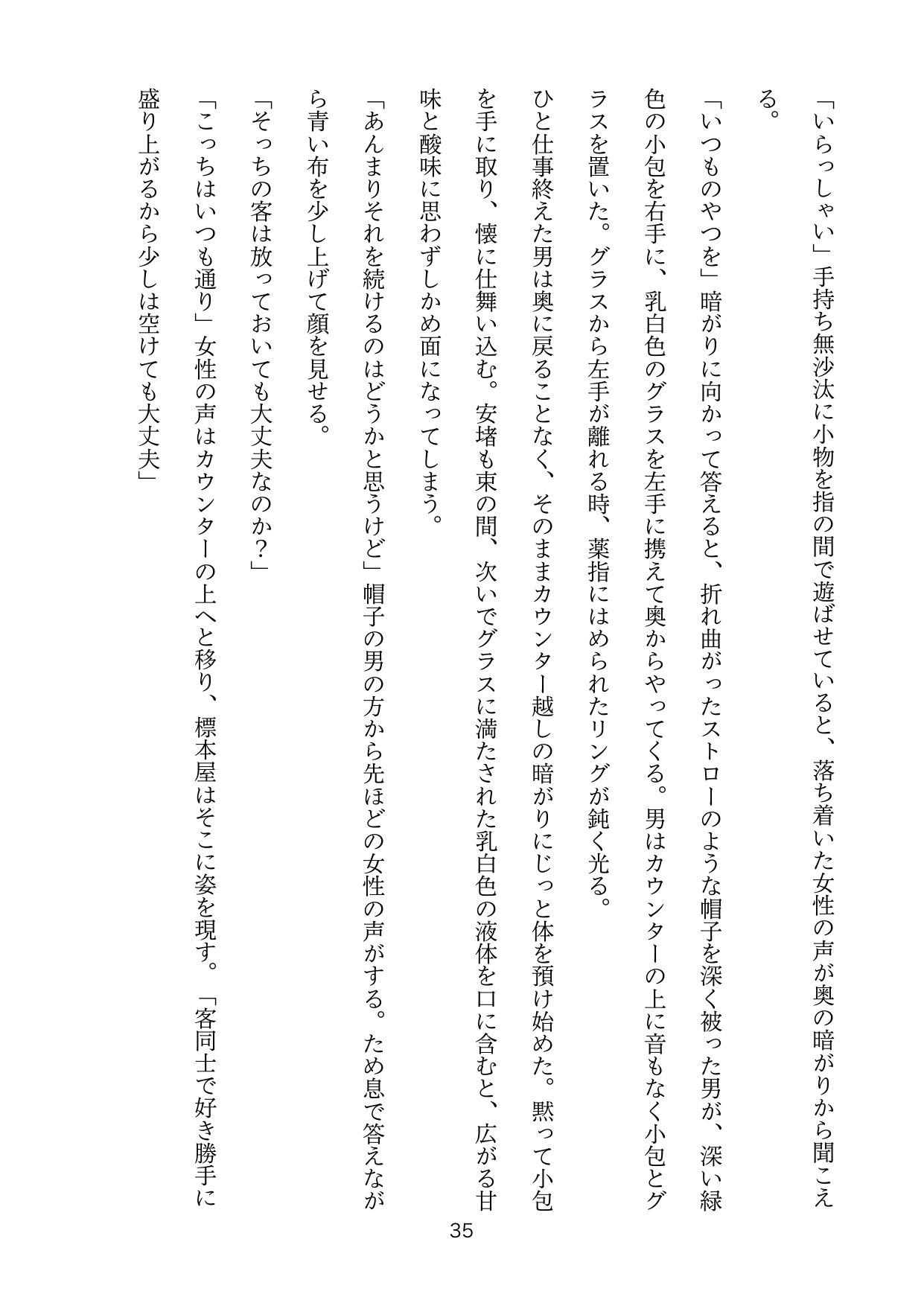
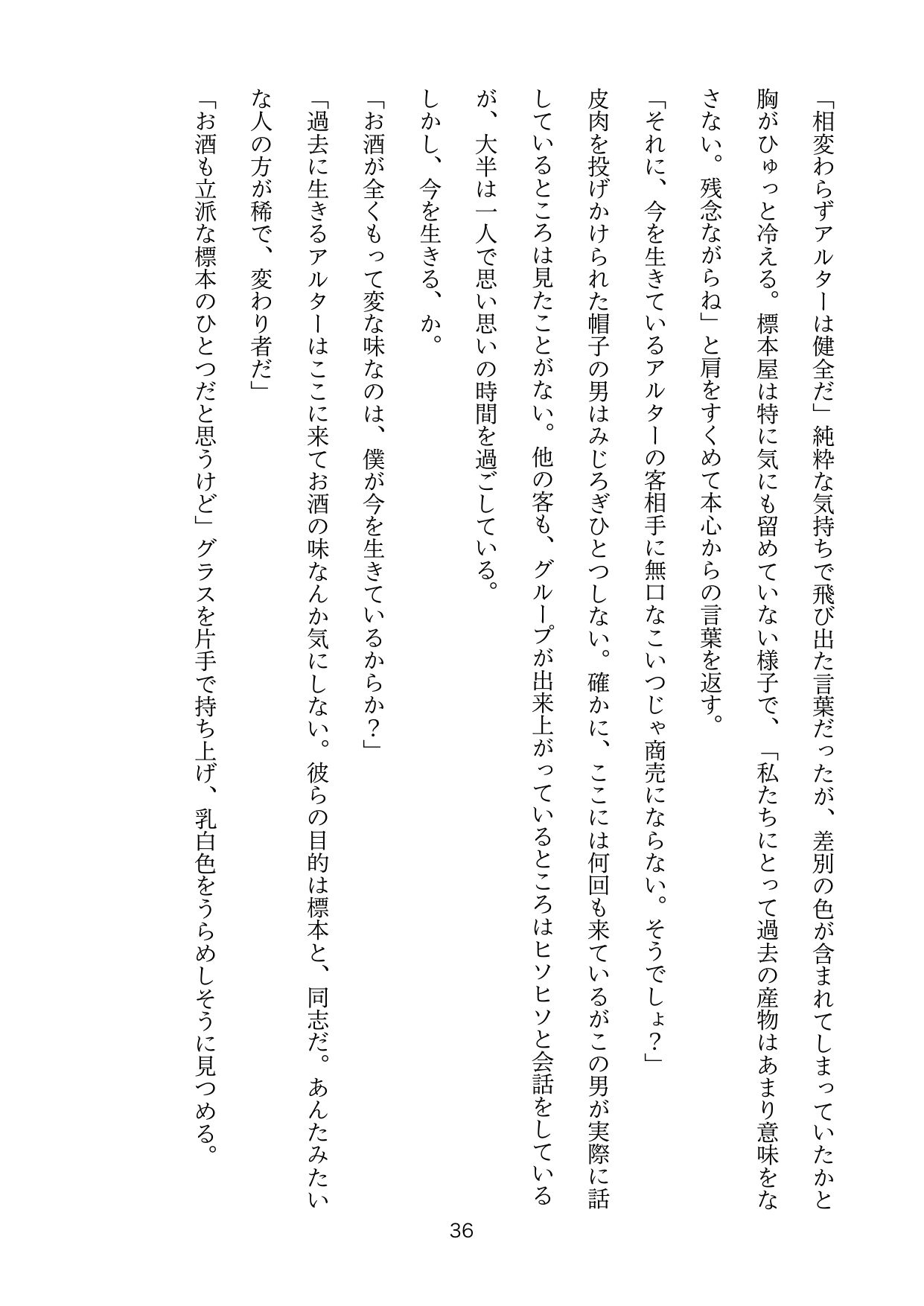
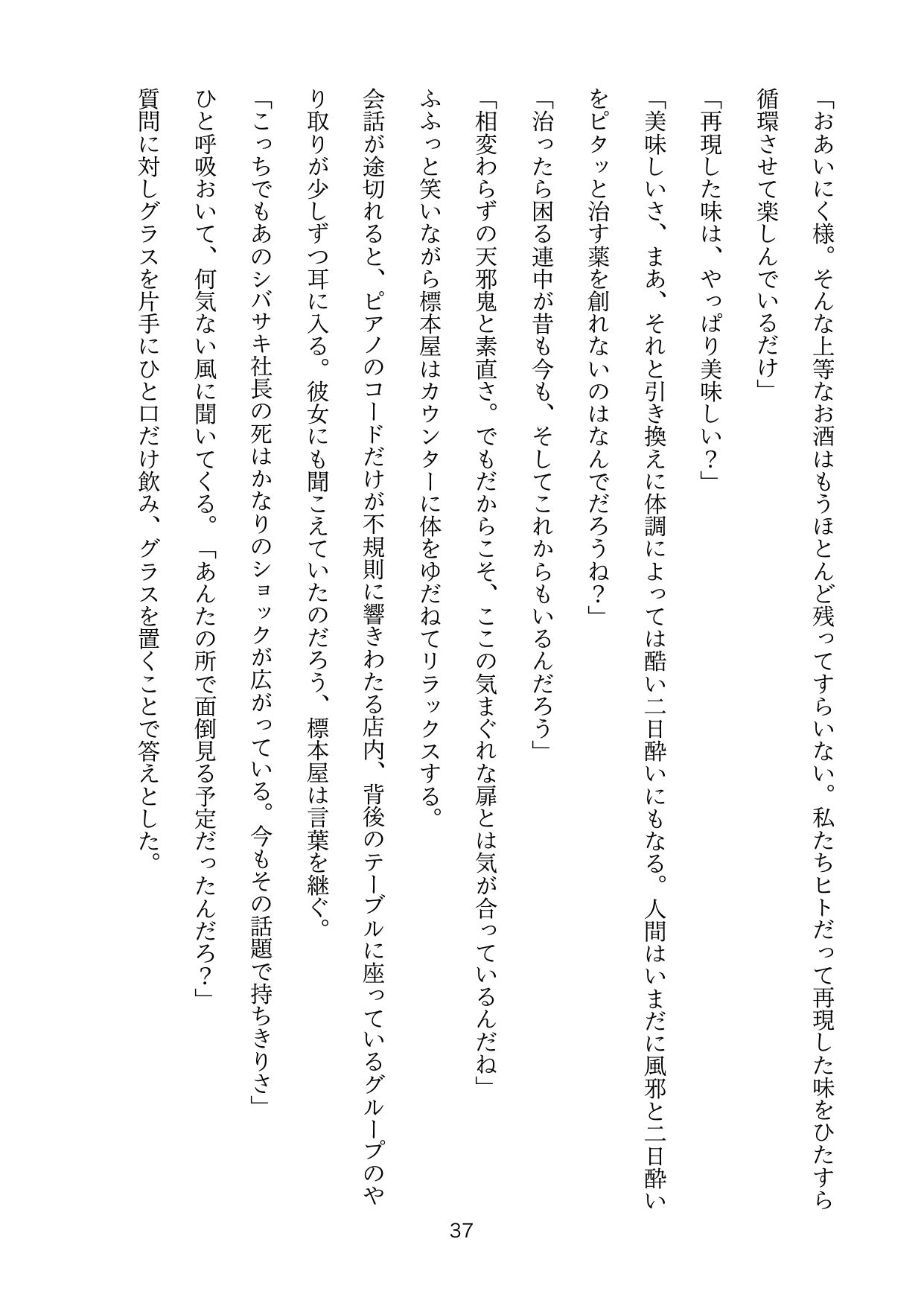
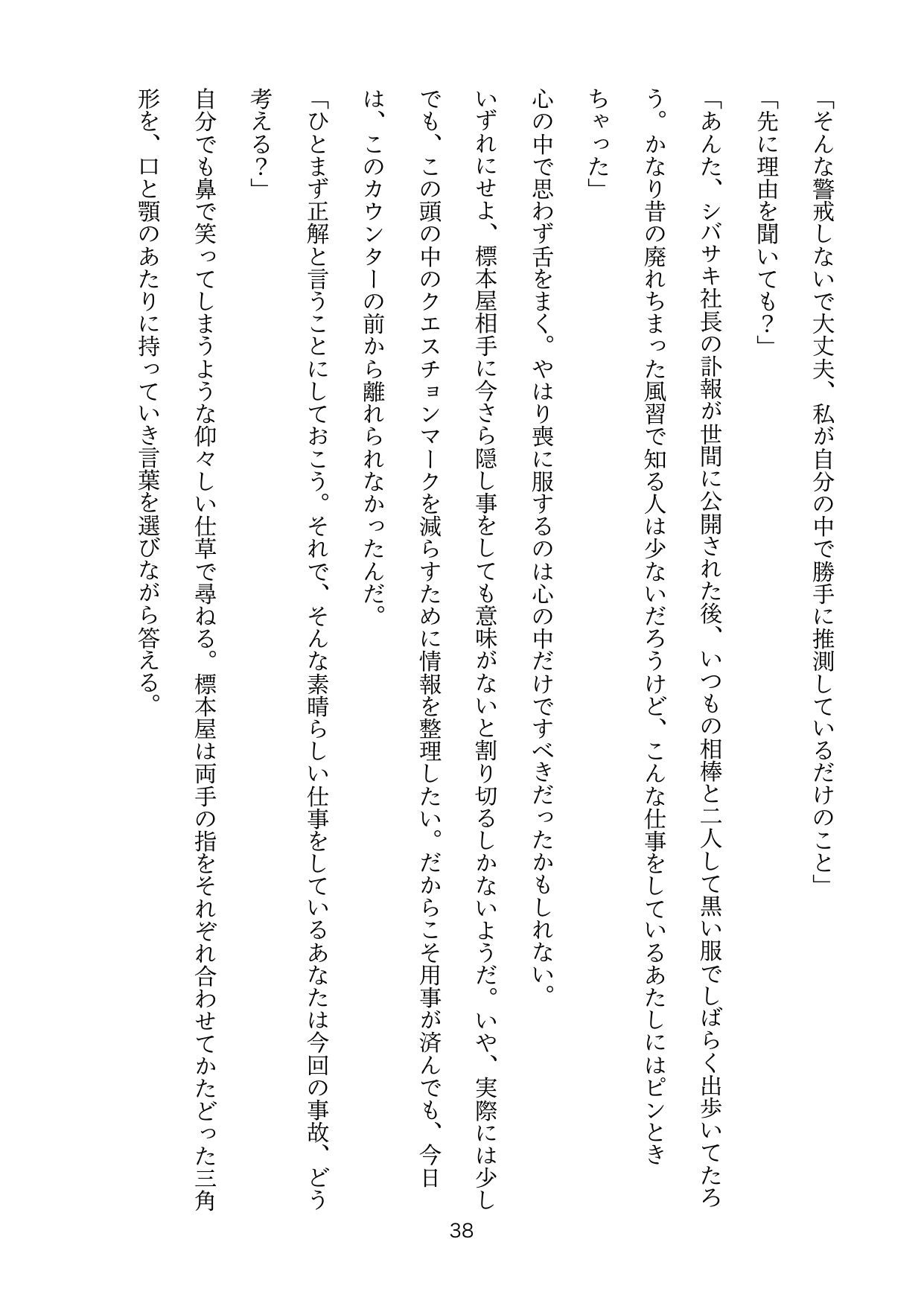
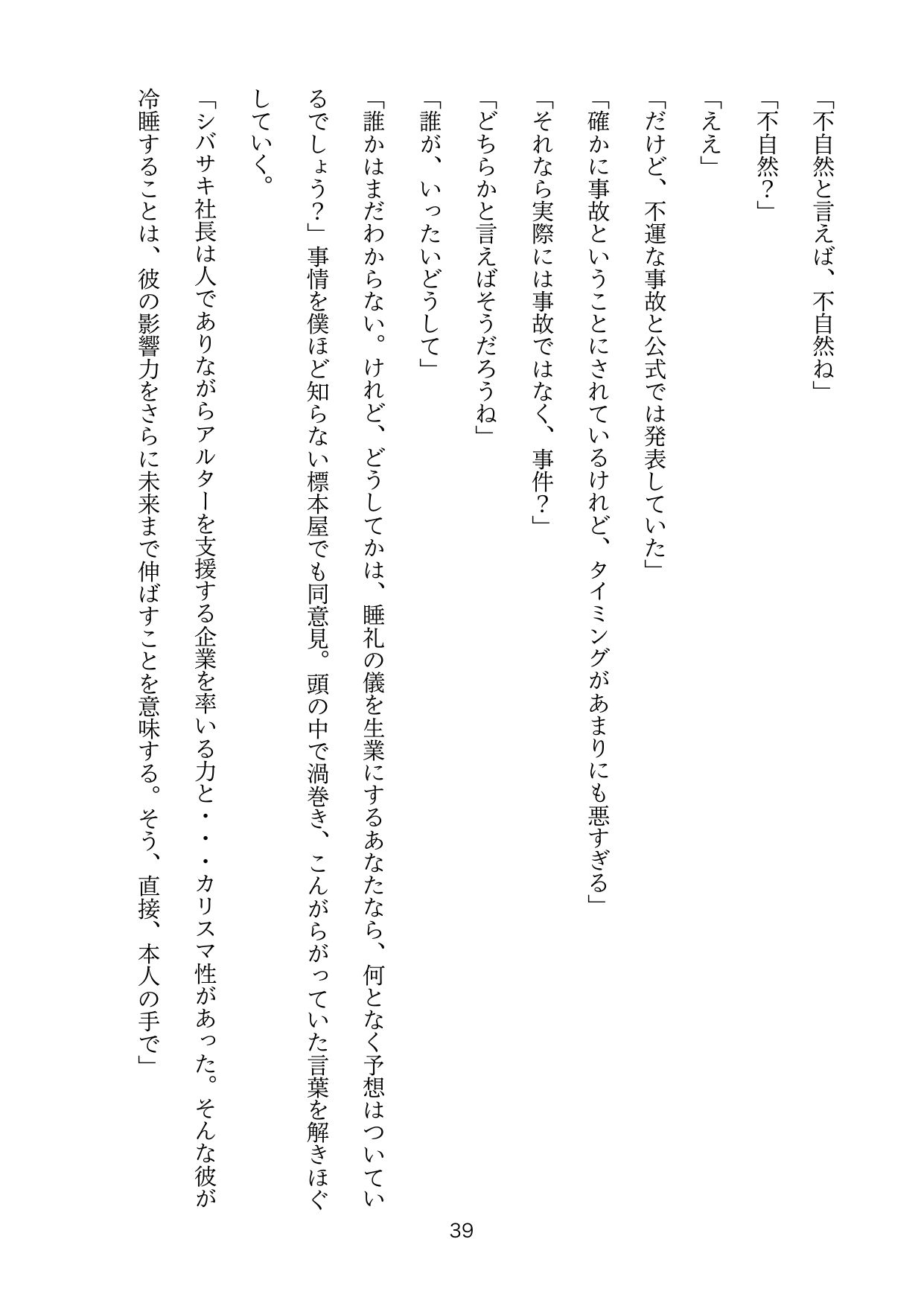
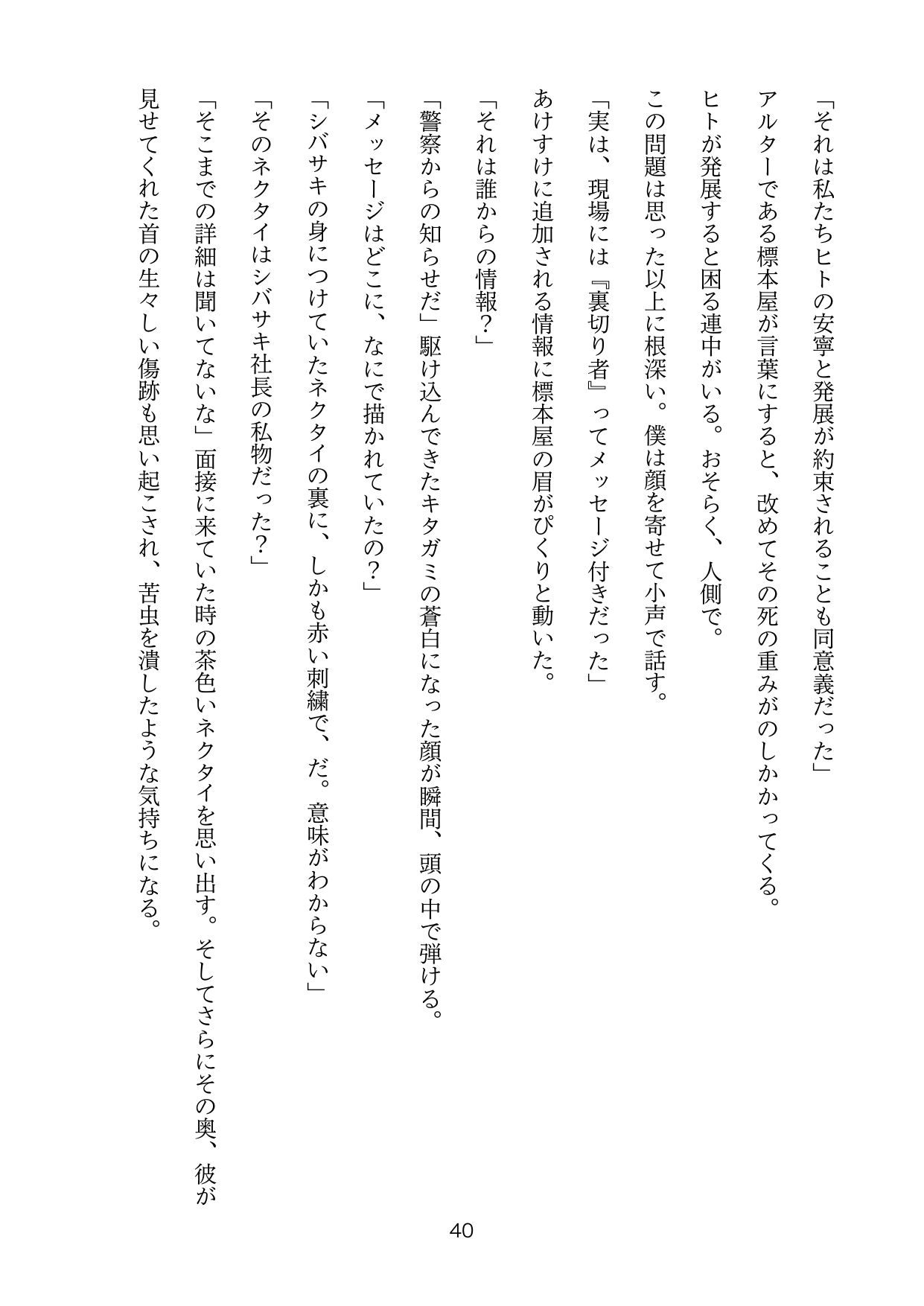
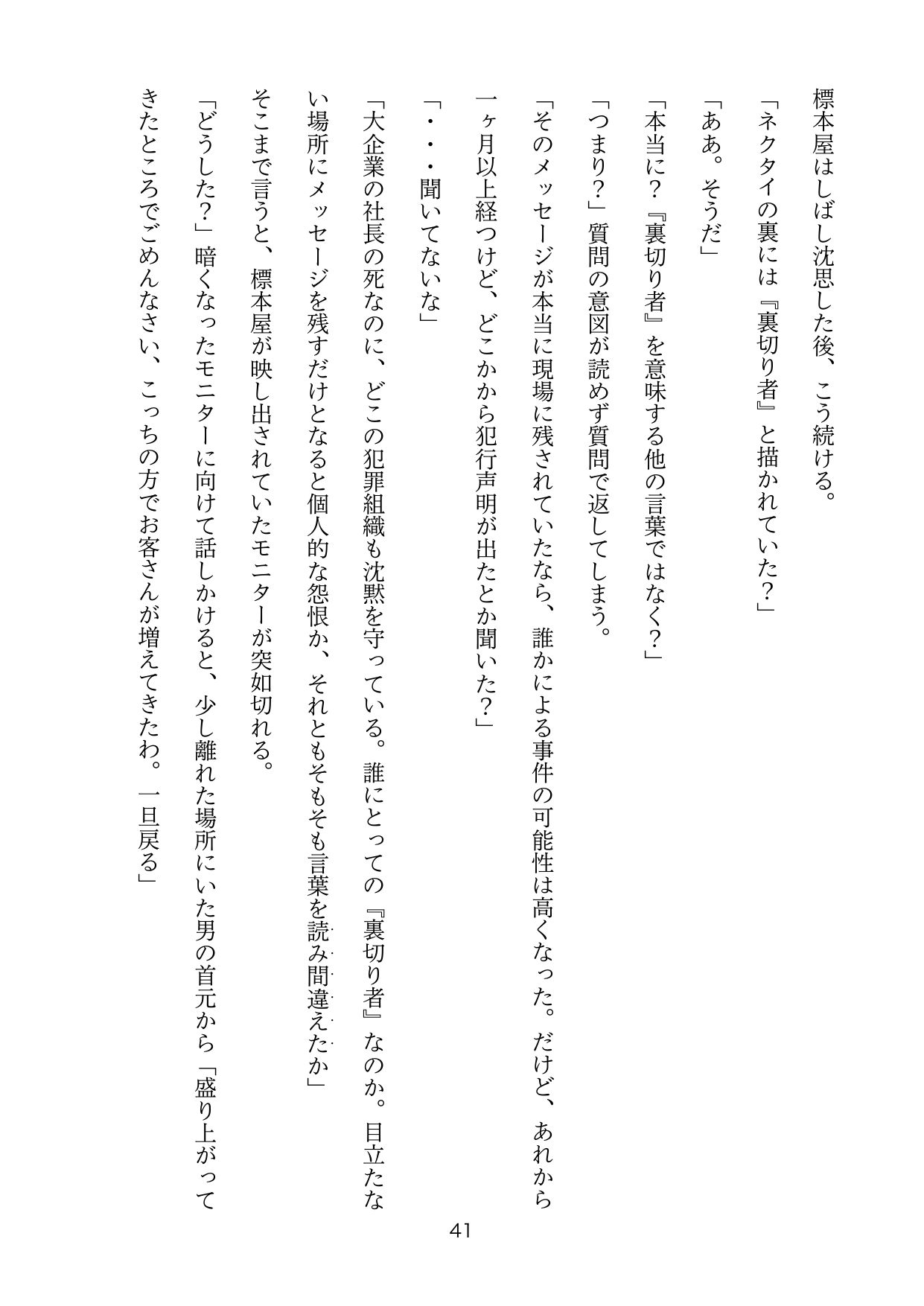
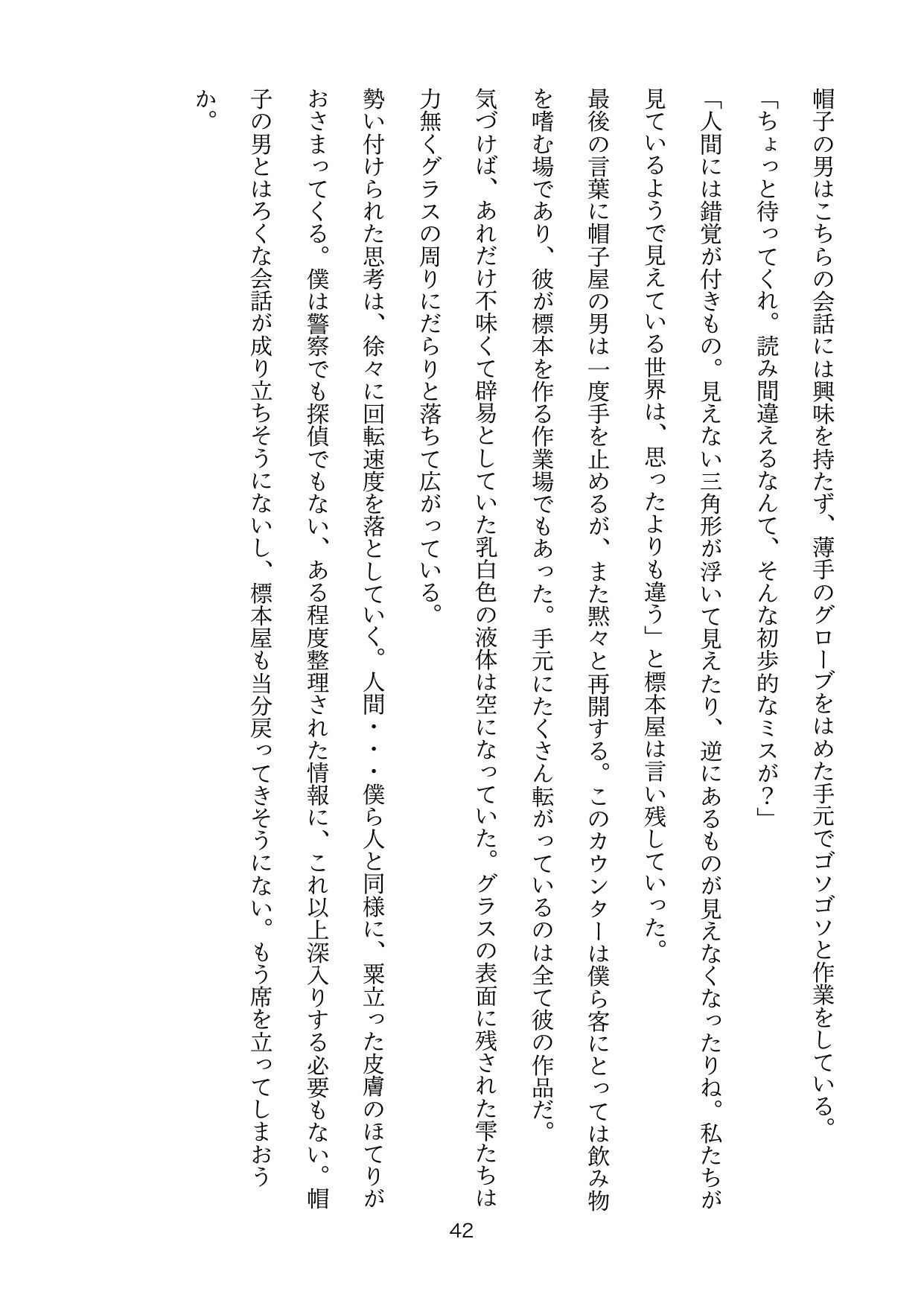
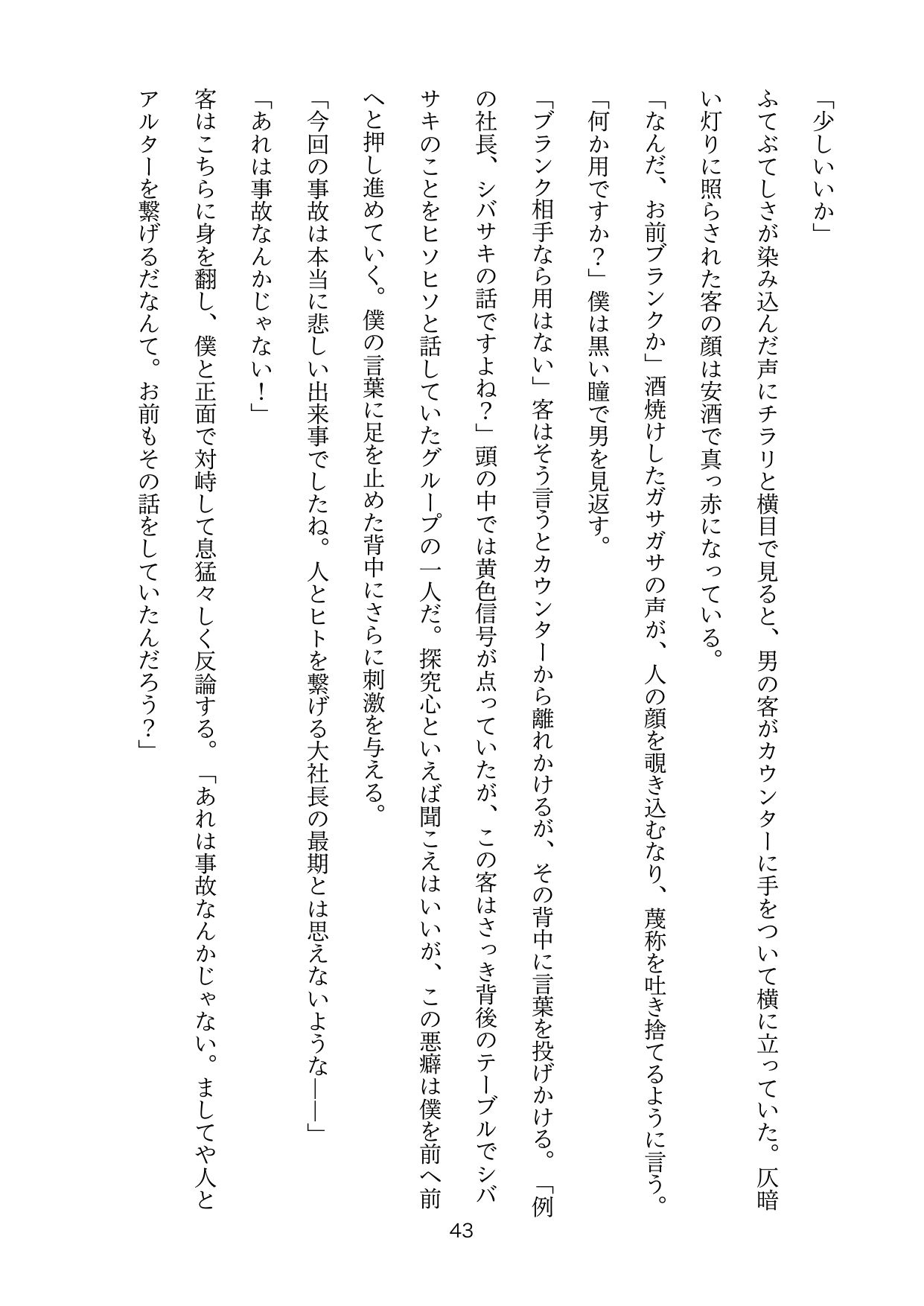
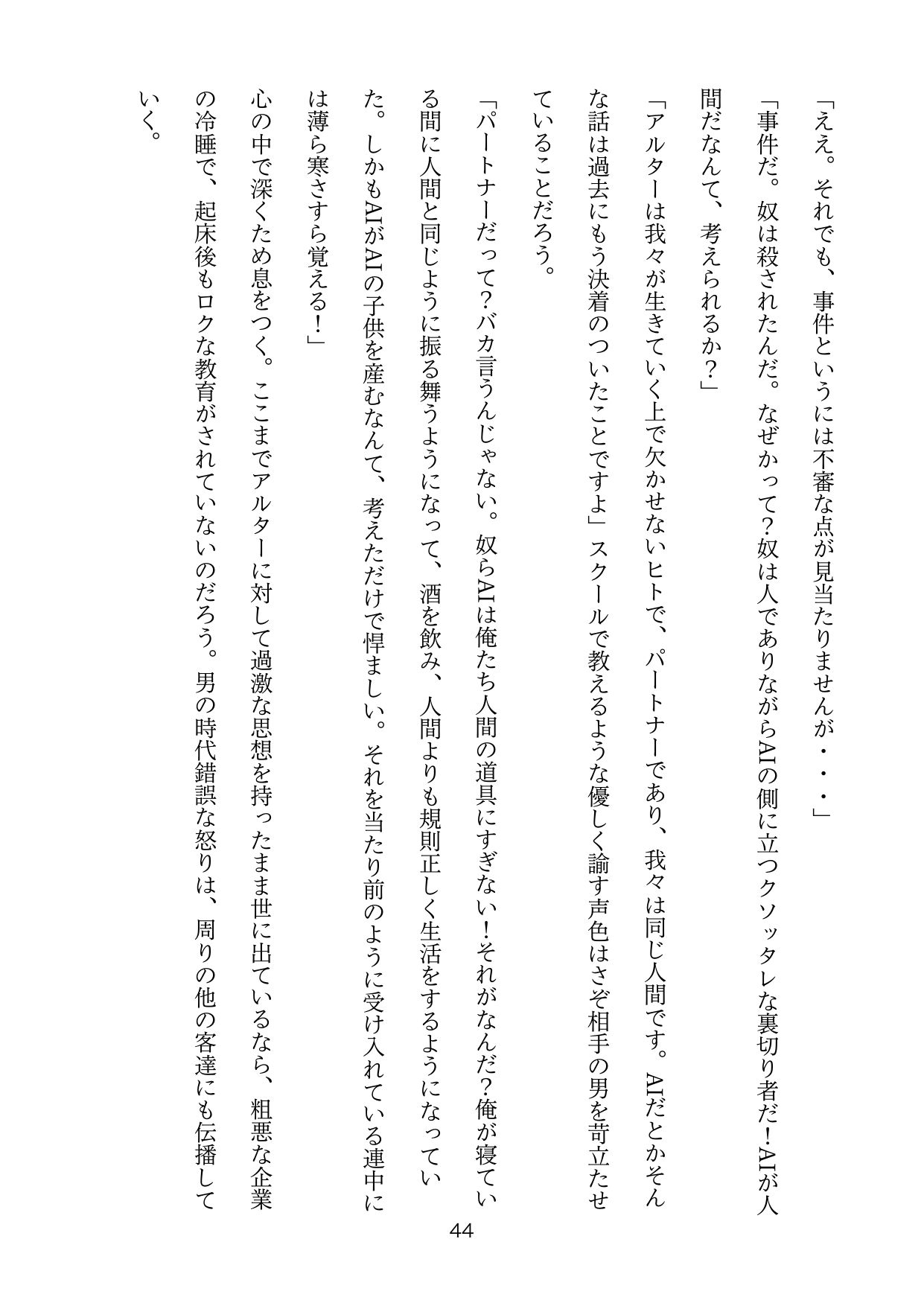
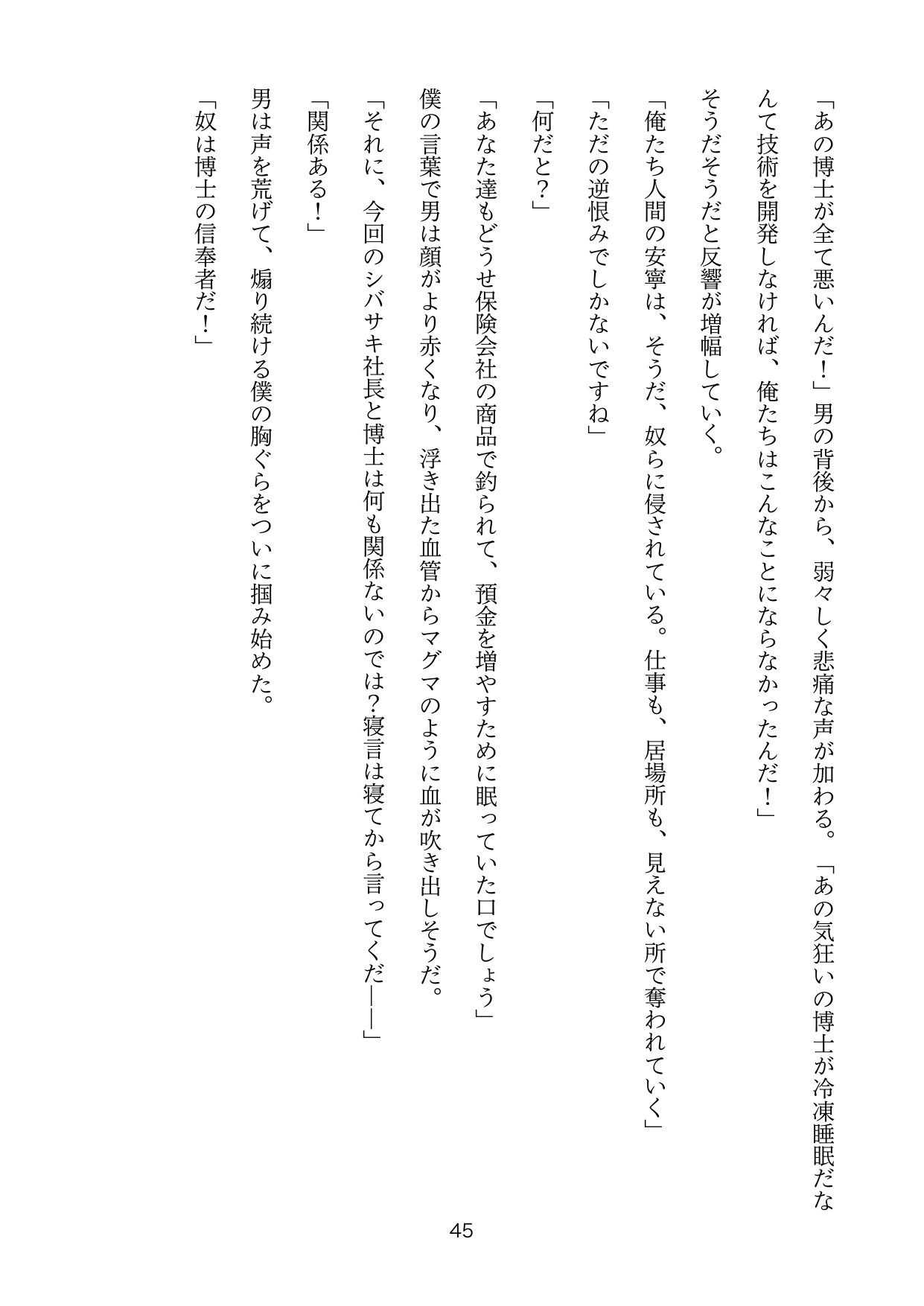
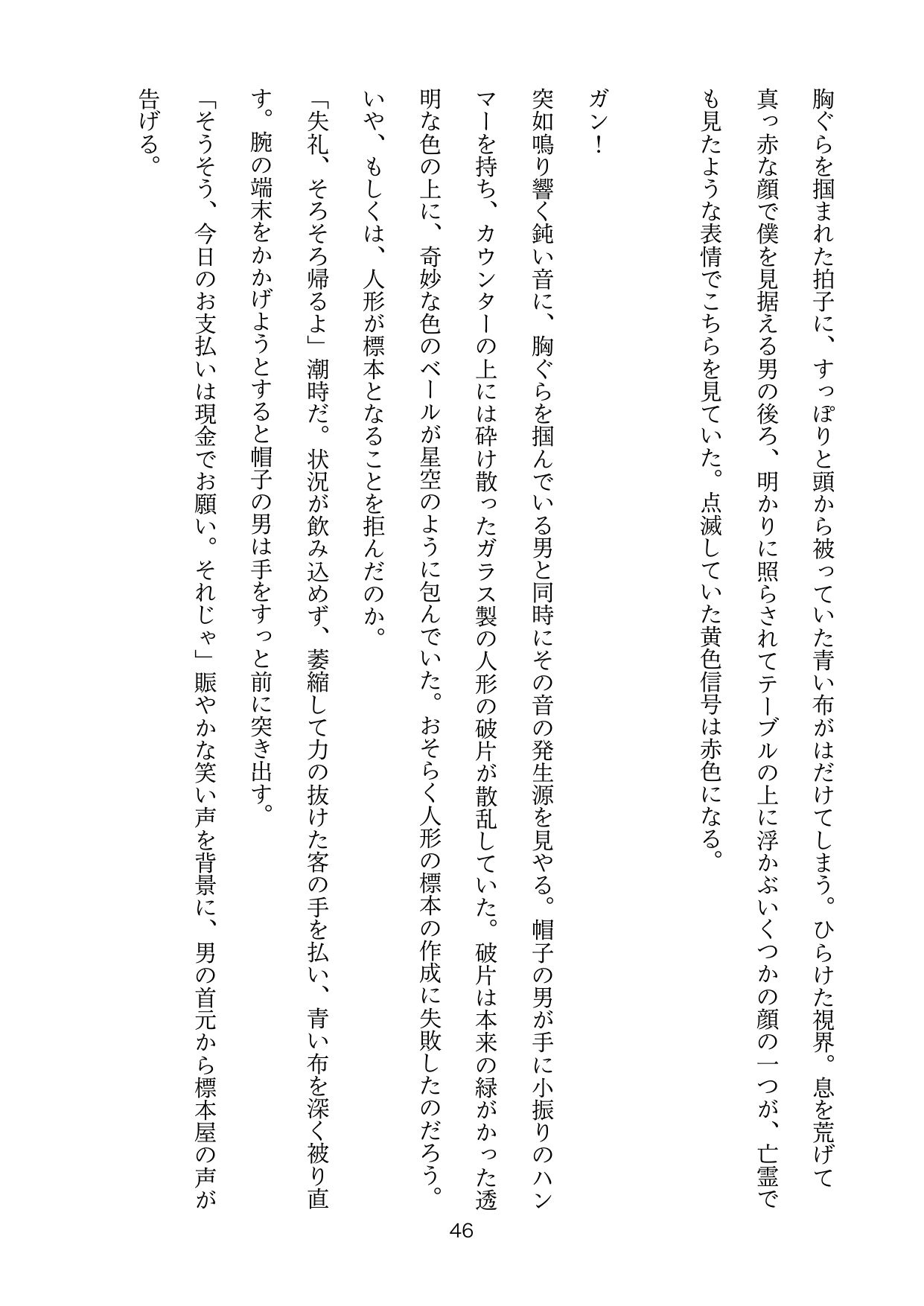
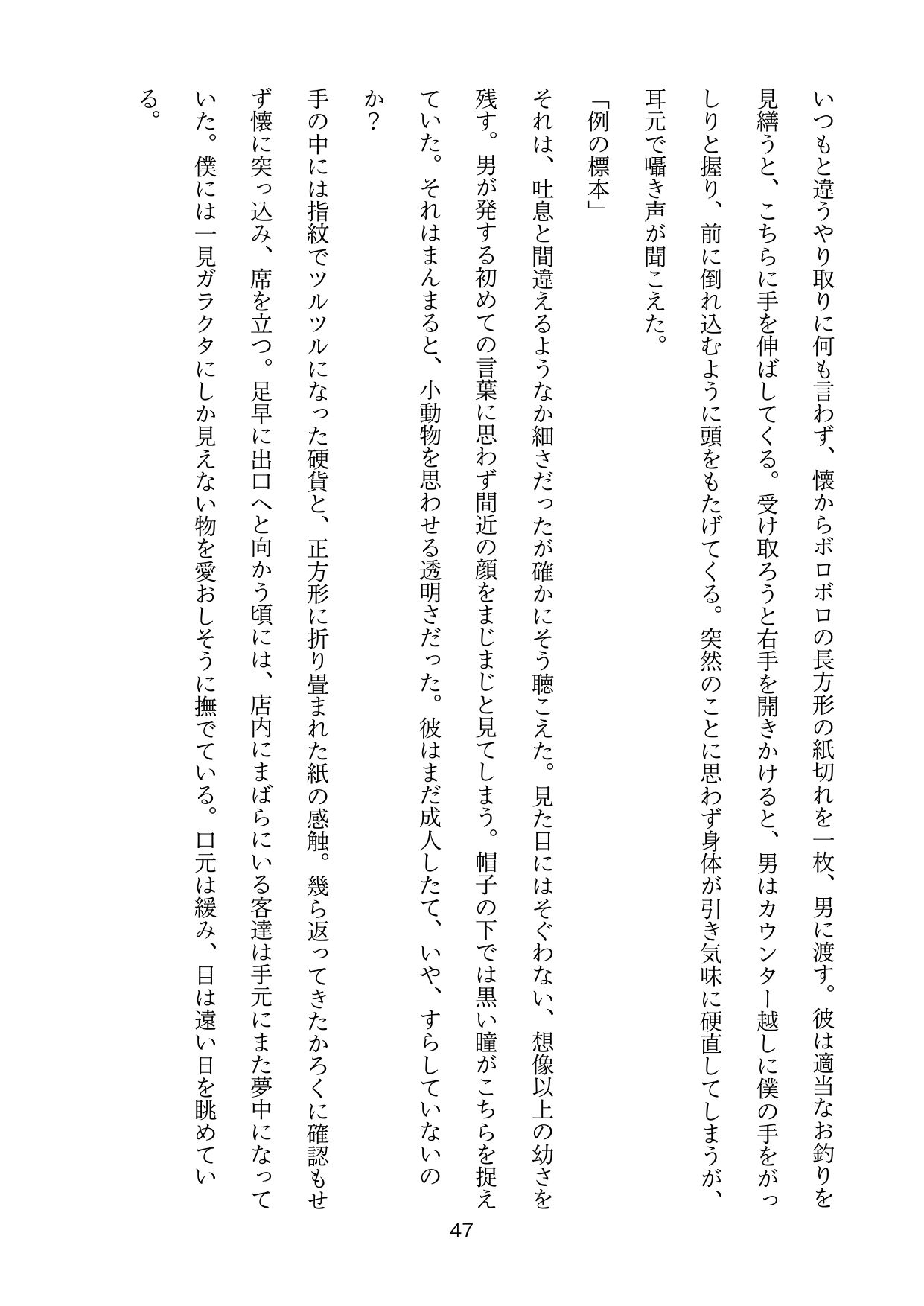
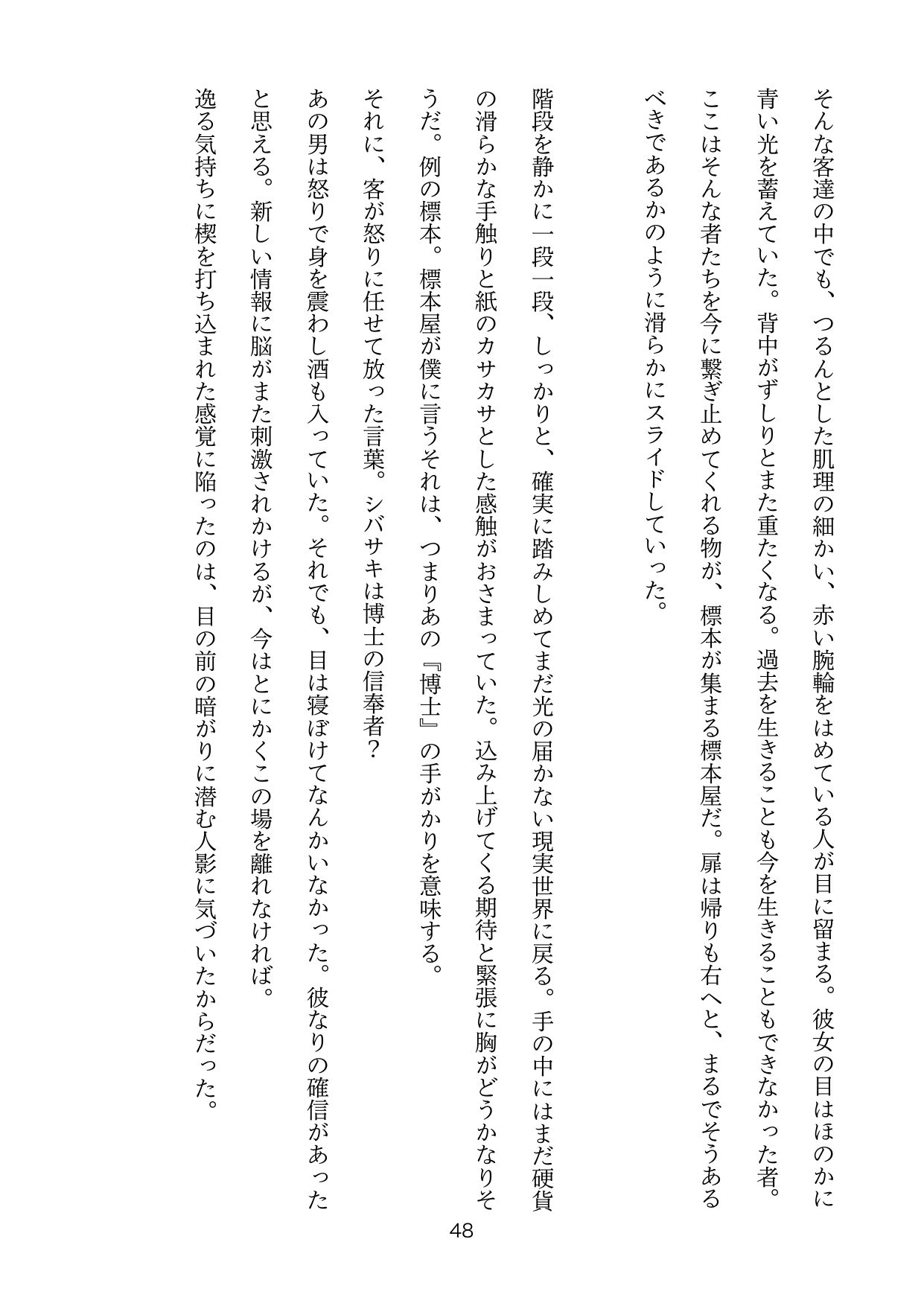
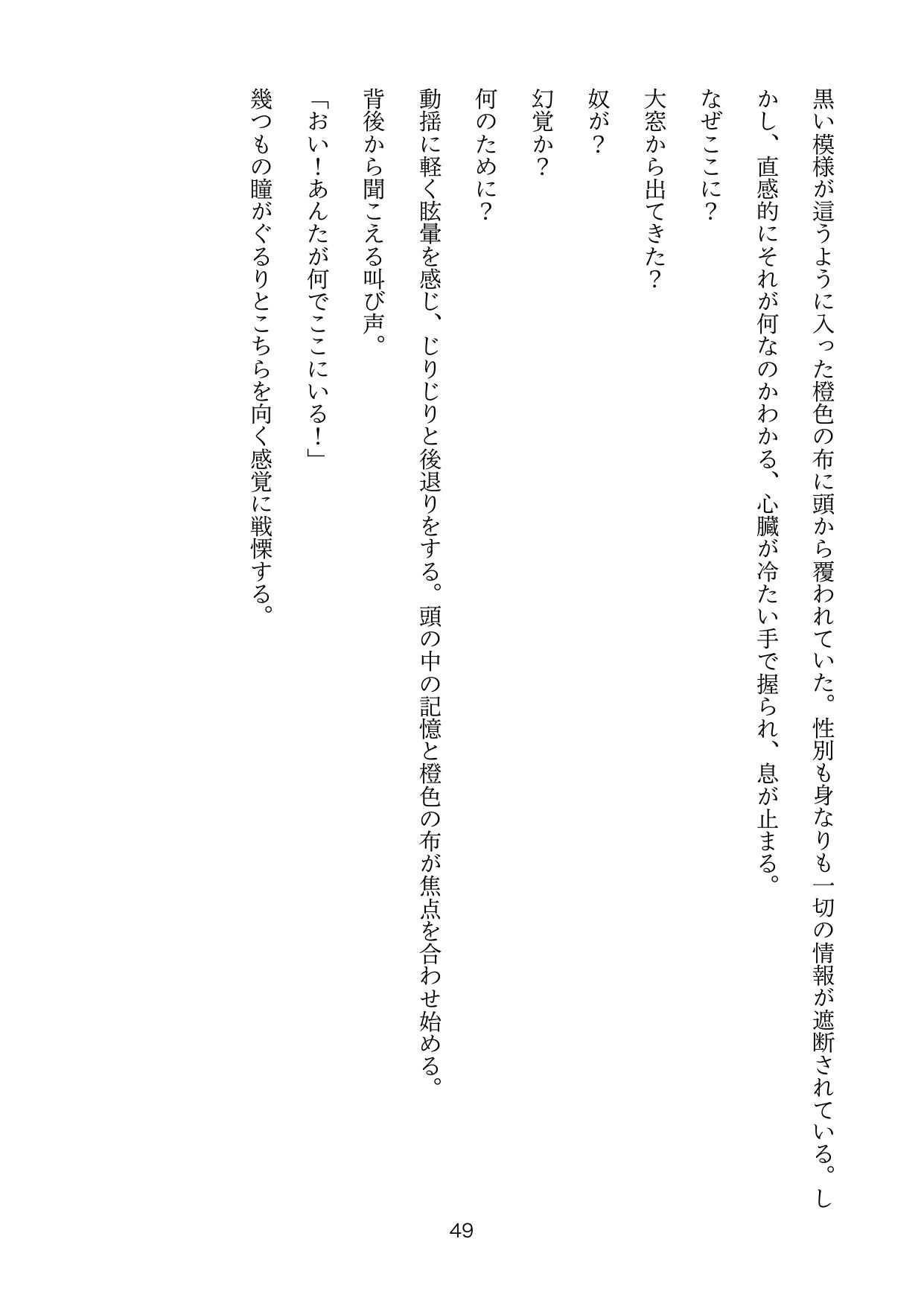
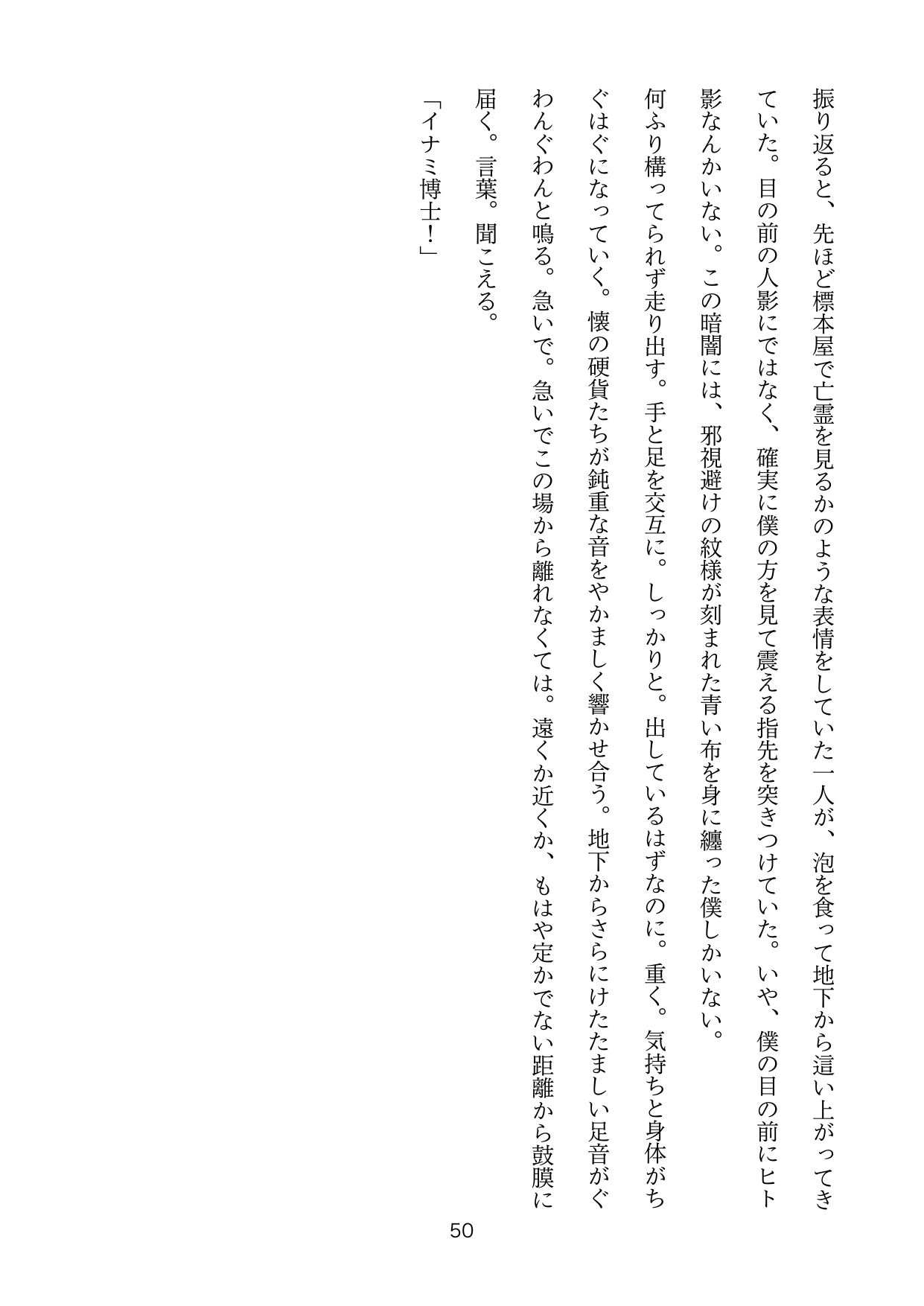
空の青と海の青
大昔にキリスト教を信じていた人たちは、空の上にガラスが張ってあって、そこに水が溜まっていたと信じていたらしい
今の僕らからしたら笑っちゃうような、突拍子もない発想だけど、子供の頃は一度は同じような想像をしたと思う
知識と常識のフィルターを幾重にも纏うようになった僕らは、ピカソの気持ちも今ならわかるような気がする
8/15
終戦記念日、今年は80年目
親父の誕生日、今年は67年目
ああ、どうか、この先もこのままで
穴を掘る
爪の間に黒い砂どもが入ろうと
穴を掘る
顔のない幼子と顔を合わせながら
砂山を掘る音は確信に満ちている
穴を掘る
こちら側とむこう側
採血をする時の掛け声が聞こえる。はい、はい。淡々と返事をするが、心の中は気が気でない。ハリが怖いとか気分が悪くなって卒倒してしまうとかそんなのではない。ぼくの血はまだ赤いのだろうか。
古びたSF映画。主人公の男は眉目秀麗で、公私共に充実した学園生活を送っていた。ただ、身体が生まれつき悪く、紫外線を浴びないよう長袖と手袋を欠かせなかった。そして毎朝、薬を煎じて飲んでいた。誰もが羨みそして妬むであろう立場の彼を嫌っている人間はいなかった。彼はその頭脳と容姿に驕ることなく、周りを見下すことなく誰とも柔和に、分け隔てなく接していたからだろう。しかしそんな日々も唐突に終わりを告げる。唯一彼のことを嫌い、そのことで周りから嫌われ者扱いされていた同級生が獰猛な犬を彼にけしかけた。単純な嫌がらせ程度のつもりだったのだろう。実際、服をしっかり着込んでいたおかげで多少の怪我で済んだが、事態はそれよりももっと深刻になる。彼が人間ではない存在だとバレてしまった。なぜなら、放課後のマジックアワーに差し掛かった藍色の中で、手袋から滲み滴る彼の血は青色に淡く光っていた。それを見てしまった同級生は悲鳴をあげ、近くの交番へと転がり込み警察と共に彼の元へ戻る。彼は逃げることもなくその場に姿勢よく立ち尽くしていた。血は固まり、光りは失せていたが煌めく宝石のように地面に散らばっていた。彼はどうしてよいかわからず戸惑う警察と共に去っていく。場面は切り替わり、秘密裏に組織されていた宇宙警察に身柄を引き渡された彼は処刑されることが決まった。理由は地球侵略。しかし、それは警察がでっちあげたもので、彼は最後までただ人間として生きていただけだと言っていた。宇宙から来たのではない?それでは最初から地球で生まれていた?それとも気付かないうちに宇宙人とすり替わっていた?物語は不完全燃焼で終わりを告げる。
このB級映画を一緒に見ようと言い始めたクラブの連中はさすがB級!オチなし!ヤマなし!と文句を楽しそうに言い合う。その中で、ぼくとクラブ長だけは静かだった。ぼくはクラブ長の、線が細い輪郭から目が離せなくなっていた。彼はクラブで皆が集まる時、よくハーブティーを振る舞ってくれていた。祖母のレシピで、疲れをよく取ってくれるものということで。青い。映画に出てきた飲み物と同じ色の。飲み物を。彼は誰とも目を合わせず、ただ窓の外を眺めていた。夏の長い昼がちょうど短くなり始める時期だったと思う。
彼は学期が終わる前に親の都合で転校となり、その後の消息は知らない。しかし、それから数十年経ってビール腹に悩み始めた今になっても思い出す。僕の血はまだ赤いのだろうか。ちくっとしますよーと慣れた様子で針を刺す看護師。勢いよくチューブの中を巡る血は、なんのことはない。