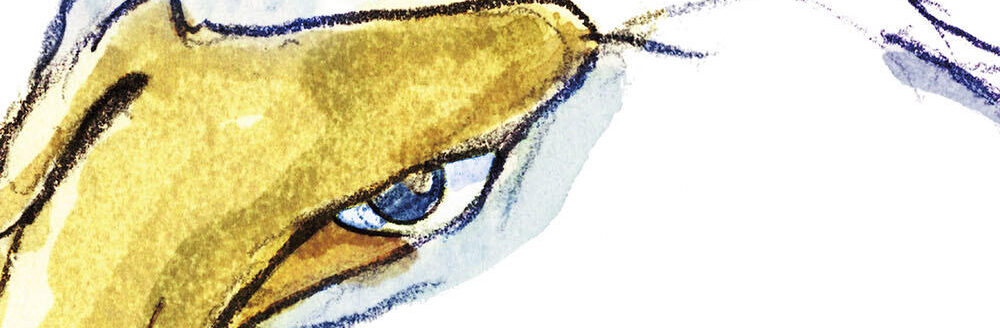時系列で話していこうと思ったが、人物に絞って話した方がまとまりが良さそうなのでそうすることにした(あまり細かく話して映画の意義を損なわせ、訴えられるのも嫌なので)。そして、まだ一度しか映画を観ていない&君たちはどう生きるかの原作と呼べる物を読んでいないため、描写や記憶に違いが発生している可能性もあらかじめお断りしておく。
以下、映画を見ていない人は読まないように。
ちなみに、前回のは此方 https://february-30.com/memory20-1/
【1】ナツコ
この物語はマヒトが異世界へと誘われることで大きく展開していくが、その展開に拍車をかける存在がナツコだ。それと同時に、話をややこしくしているうちの1人でもあるので、まずはこの人物を中心に考察しようと思う。
マヒトが異世界に踏み込むきっかけとなったのは、つわりに苦しんでいるはずのナツコが森に消えていったことだ。のちに、ナツコを誘い出したとマヒトはアオサギに詰めるが、私にそんな力はありませんとアオサギはいう。
それならば何故ナツコは森へと向かい、異世界の産屋に引きこもったのか?
これを紐解く鍵は三つ。
一つ目はキリコの発言。マヒトを引き留める際、血縁者にだけ声が聞こえると言う。そしてそれは罠だ、と。この声がアオサギのものなのか大叔父のものなのかははっきりとしないが、それならナツコもマヒトと同様に大叔父の血縁者であるので何かしらの声が聞こえるはずだ。冒頭でアオサギのことを「覗き屋の」アオサギと呼んでいるので、何かしら普通ではないと感じていたのだろう。アオサギは誘い出したのは自分ではないと言うが、「アオサギが言うことは全部嘘だというのは本当だ」のようなニュアンスのことを言うので、大叔父が直接誘い出したというよりはアオサギを通じてマヒトと同様にナツコを誘い出したのだろう。
二つ目は森に入っていくタイミング。マヒトは父に何回か催促されようやくナツコのお見舞いに行くが、一度挨拶するとすぐに帰ってしまう。その後、弓矢作りに夢中になるマヒトを尻目にナツコは森へと消えていく。新しい母として頑張ろうとはしても、姉の代わりになりきれないのだろう。転校早々喧嘩をし大怪我をして帰ってくるマヒトに戸惑いと悲しみも感じていたかもしれない。マヒト側もナツコを母とは認めれず、距離感を持って接している。実際マヒトは塔に入った後、ナツコのことを聞かれても母親とは説明せず父が好きな人としか言わなかった。そんなナツコとマヒトのすれ違いにアオサギを通じて知った大叔父は、なかなか思うように塔の世界へ来ないマヒトを誘き出すためにナツコに語りかけ(もしくは一つ目の鍵で説明したようにアオサギが)、現世から離れた塔の世界へ来るように仕向けたのではないだろうか。言うなれば奥さんが実家へ避難するかのような感覚…?
そしてマヒトがナツコを追いかけてくるのを大叔父は確信していた。何故ならマヒトにはナツコが自分の母と重なっていたからだ。その描写はいくつかある。塔の中に入ると、アオサギはソファの上に横になっている人がオカアサンだと言う。つかつかと歩み寄り背中越しに横顔を見るとマヒトは涙を浮かべ、お母さんと思わず肩に触れ呼びかける。しかし、服装は森に入っていくナツコと同じ物で、アオサギの言うオカアサンがその場面ではヒサコなのかナツコなのかわかりにくく、どちらともとれそうだ。そしてマヒトの位置からは顔はよく見えていないはず。恐らく、ナツコを模した人形?をマヒトは自分の母親と間違えている。間違えてしまうのも無理はない。冒頭ナツコに初めて会った時、マヒトは自分のお母さんとよく似ていると感想を述べているからだ。
ナツコが塔の世界に来た理由と経緯は二つ目の鍵で推測してみせたように、簡単に言うと大叔父がマヒトを誘き出すため。そして物語の後半でわかるように、マヒトを誘き出したのは自分の後継者になってもらうためだった。しかしそうなると、大叔父がナツコを手厚く保護し、石の産屋にナツコが籠る理由がよくわからなくなる。
三つ目の鍵はその疑問を解消してくれるはず。つまり、大叔父はナツコをマヒトを誘い出すためのエサにするだけでなく、ナツコの産む子が後継者になりうる可能性も捨てていなかったからではないか?そう思う理由は①インコたちはナツコが子供を宿すから食べることができないと言う②石(恐らく大叔父の意思でもある)がナツコを連れ戻しにきたヒミとマヒトを歓迎してない③初めはマヒトを拒絶するナツコがお母さんと呼んでくれたマヒトに向き合おうとすると、紙の龍がナツコにも襲いかかる。つまりナツコは自らの意思で積極的に産屋にこもっていない④産屋に入ることは塔の世界でタブーとされ、インコ達も入ることができない。塔の世界の殿様は大叔父なので、そのタブーを決めたのも大叔父だろう。
以上のことからまとめると、大叔父の血縁者であるナツコは新しい子を宿すがマヒトとの関係に折り合いがつけれず、弱っているところに大叔父に誘われマヒトを塔の世界に後継者にすべく連れてくるためのエサにされる。石の産屋で厳重に保護していたのはいずれ産まれる子が後継者になることも想定していたため。となる。情報は少なく断片的であるため空想の部分ばかりになるが、一度映画を観た自分の中ではこうおちついている。しかし、それでも疑問点は残る。
・何故大叔父に後継者として呼ばれたのに、大叔父の支配下にあるはずのインコたちが襲ってきた?
・何故ナツコやヒミは血縁者なのにそもそも後継者に選ばれなかった?
・塔の世界は地獄のような意味合いが深いが、そんな世界で出産をすることは何を意味するのか?
地獄。輪廻転生。黄泉の国。天照大神。カグツチ。この映画はマヒトの物語でもあり、ナツコの物語でもある。不思議な出来事を通じて家族の絆を作り深める、とも捉えられる。君たちはどう生きるか。次回も考察がたまれば載せてみようと思う。
〈追記〉
今回のジブリ映画は余白の多い映画だ。キャラクターのさりげない、ふつっとした独り言のような言葉が未知の世界観を深めている。その世界で生きている人間だからこその、聞き逃してしまいそうなぐらい自然な言葉。それらの使い方が上手いのは魔女の宅急便、千と千尋の神隠しや、ハウルの動く城に通ずるものがある。わからないもの、整合性がないものはこうやっていくらでも考えて補完してみる楽しみがある。